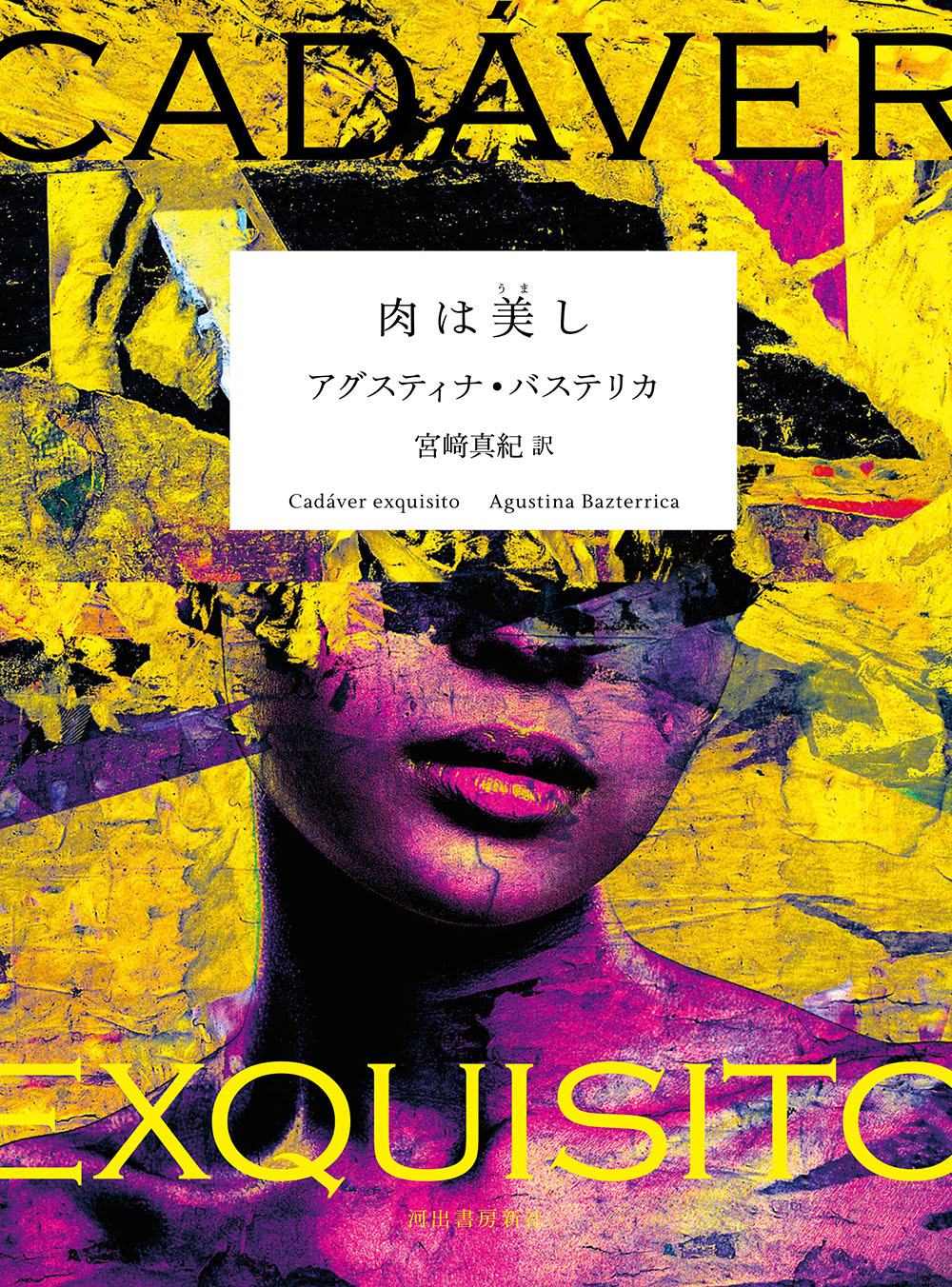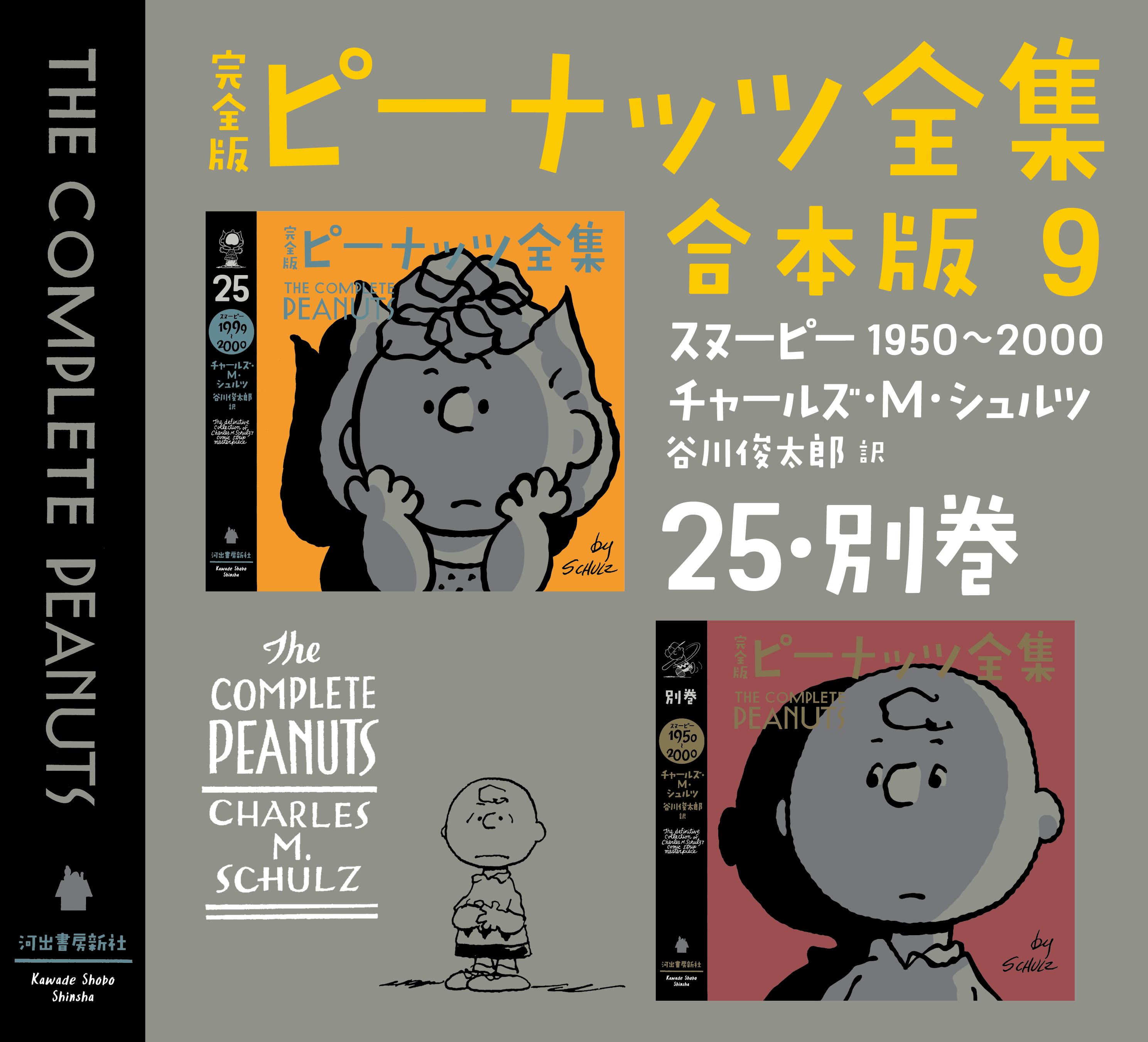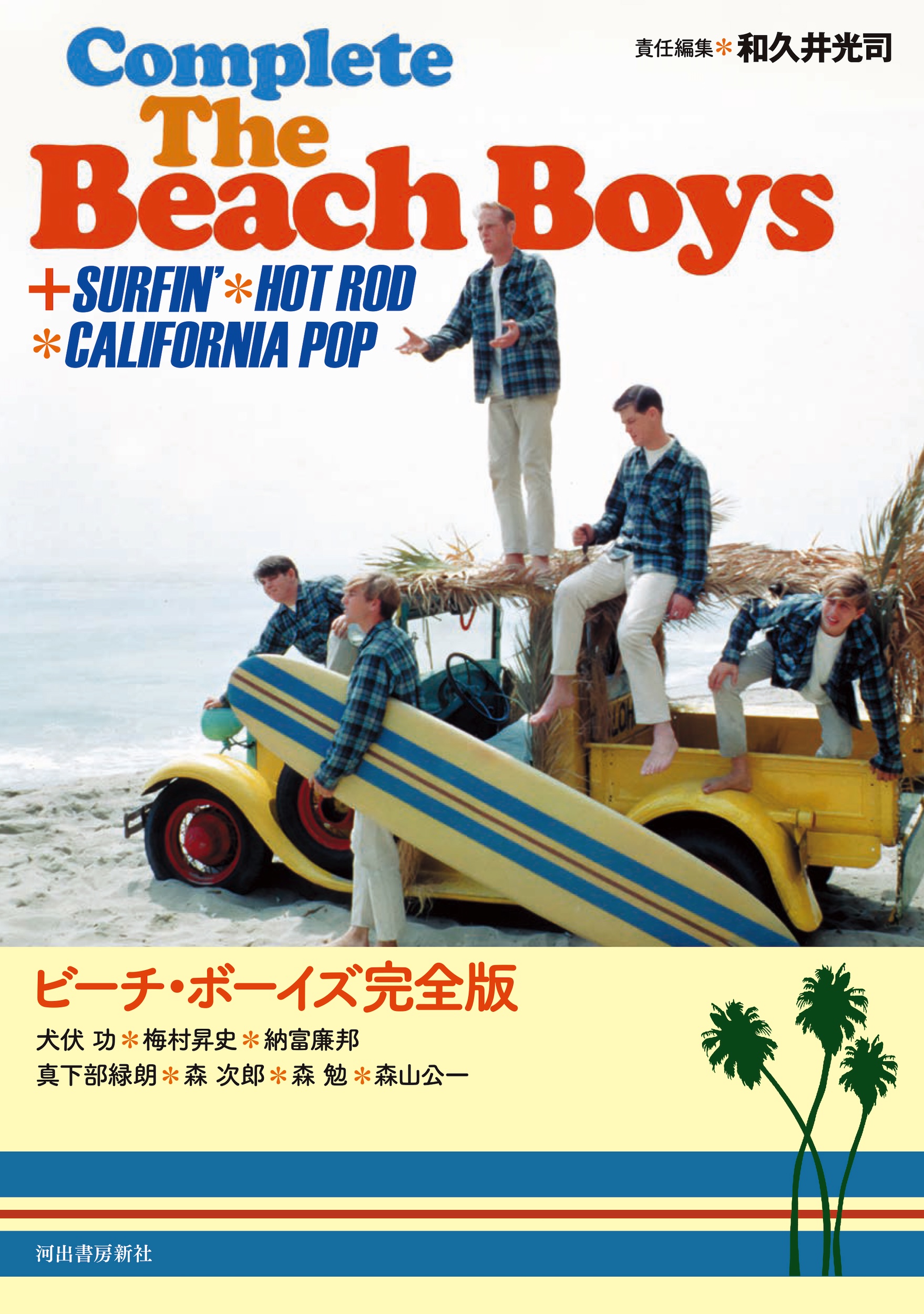単行本 - 外国文学
『黄色い雨』の著者フリオ・リャマサーレスの短篇を無料公開!クリスマスには決して読めない、クリスマス・イブの物語。 - 3ページ目
フリオ・リャマサーレス
2022.05.23
四十年のあいだに(二人が結婚してそれだけの年数が経っていた)、女主人はご主人を意のままに、すべての面で自分の思い通りにするようになっていた。ただひとつ、日曜日のミサに同行することにだけは頑として首を縦に振らなかった。ご主人は無神論者ではなかったし、宗教に背を向けていたわけでもない。ミサなどどうでもよかったのだ。ご主人が自分の部屋に迎え入れていたたったひとりの客というのが、実は町の教区司祭ドン・マルセリーノだった。女主人に背中を押されていた司祭は、チェスを指しながら辛抱強く説得に当たったが、ご主人はうんと言わなかった。教会に行くことを拒み続けたのは、ご主人にしてみれば自身の矜持を守ると同時に、過去四十年間言いなりになるよう強いられてきたことに対する反発でもあったとぼくは睨んでいる。女主人は何度も説得しようと試みたが、結局ご主人は首を縦に振らなかった。かつて女主人の両親は日曜日になるとそろって教会に足を運んでいたが、自分たちにはそれができないのだと認めざるを得なかった。女主人としてはクリスマス・イブの日、夕食を終えたあとに家族そろって深夜ミサに出席したいと思っていたから、夫が首を縦に振らないことだけはどうしても許せなかった。
一九七一年のクリスマス・イブに主人夫妻の間で持ち上がった口論は、それまでにないほど激しいものだった。ただ、それが七面鳥のせいなのか、単に起こるべくして起こったことなのかは今もってわからない。
クリスマスの時期に市場で七面鳥を買ってお祝いをするのが、毎年の習わしになっていた。クリスマス・イブの日、女主人は七面鳥を絞める前に、味と香りが鳥の肉にしみこむように酔っぱらうまでアニス酒を飲ませるように言いつけた。その儀式には家族の者はもちろん、使用人も含めてわれわれ全員が参加したが、酔いの回ってきた七面鳥の足取りがだんだんおぼつかなくなり、ついには本物の酔っぱらいのように千鳥足で台所の中を歩き回るのを見て大笑いしたものだった。けれども、あの年の七面鳥にアニス酒を飲ませる儀式はいつもと違った。七面鳥だけでなくアニス酒のボトルも用意してあり、あとは七面鳥を酔わせるだけでよかったのだが、あの日はミゲル坊ちゃんの到着が遅れた(本人の言うところでは雪のせいだったそうだ)。われわれは全員で坊ちゃんを迎えに出て、荷物を家に運び込む手伝いをした。その間にご主人はとんでもないことをやらかした。坊ちゃんは、家族はもちろん使用人にもお土産をいつも用意して帰ってこられるので、ぼくたちはひとり残らず迎えに出た。あとに残されたご主人は、その隙に七面鳥と一緒にアニス酒の瓶を空にしてしまったのだ。われわれが台所に戻ってみると、女主人が卒倒しそうになっていた。今でもはっきり覚えているが、女主人が床に倒れないようドーニャ・アナが懸命に支えていた。正直言って、女主人が卒倒してもおかしくない状況だった。というのも、ドン・グセンドと七面鳥がまるで嵐の夜を辛くも生き延びた仲のいい友人のように、踊りながら台所のテーブルのまわりをぐるぐる歩きまわっており、しかもご主人は大声で狂熱的なバイヨン[一九五〇年代に流行したラテンアメリカ起源の新しい音楽]を歌っていたのだ。
「混血の女[ムラータ]はエデンの真珠、混血の女は美人でダンスがうまい、混血の女はエデンの真珠、混血の女は美人でキスがうまい……」
その夜の夕食会は忘れられないものになった。テーブルの一方の端に座った女主人は、黙りこくったまま何か考え込んでいたが、その目は怒りに燃えていた。反対側の端に座っていたご主人の方はさらに酔いがまわり、ナイフで皿を楽器代わりに叩きながらあの狂熱的なバイヨンを小さな声で口ずさんでいた。この二人に挟まれた家族の者は料理皿を食い入るように見つめるばかりで、ミゲル坊ちゃんでさえ一言も口をきかなかった。その夜は、さすがの女主人もクリスマス・イブの深夜に行われるミサに出るつもりがあるかどうか尋ねなかった。もちろん、尋ねようなどと思ってはいなかったし、あの場の状況から考えて少なくともその年の深夜ミサに出席すると言い出す可能性は万にひとつもないだろうと考えて、それには触れなかったのだ。ただ、夕食会が終わり、われわれ全員が家を出て教会へ行こうとしたときに、女主人は憎しみを込めて夫にこう言った。
「いいこと、グセンド」そこで女主人は一呼吸おくと、ご主人が自分の方を振り向くのを待った。「あんたのレコード・プレイヤーは、さっき窓から投げ捨てたからね」
そのあと、毅然とした態度でほかの者にこう言った。
「さあ、みんな、行くわよ」