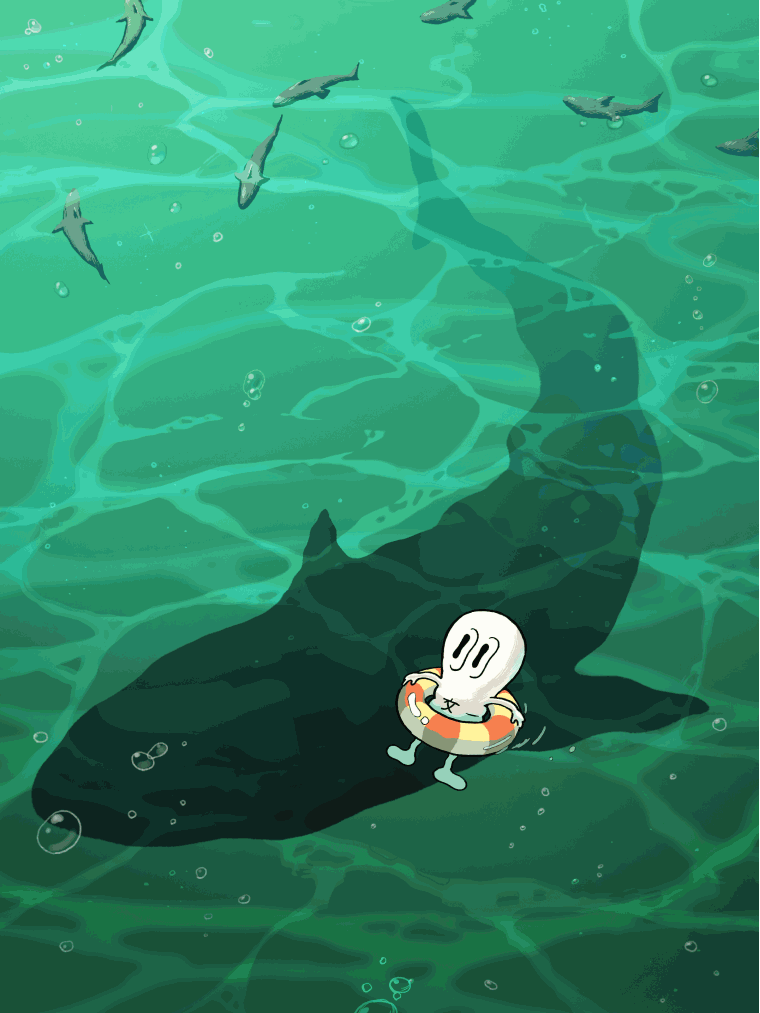単行本 - 日本文学
【劇場アニメ犬王公開直前対談】消えた存在をどう描くか ―「犬王」が蘇らせる表現の初期衝動★湯浅政明×古川日出男 - 2ページ目
湯浅政明×古川日出男
2022.05.27
消えていくものの側に立つ
湯浅 南北朝から室町時代初期というのはちょうど歴史の変わり目で、はじめて日本がひとつにまとまろうとしたときなのですが、時代考証の先生によると、それまで絵画に描かれていた、たとえば乞食とか河原に住んでいた人たちのことが描かれなくなったらしくて。歴史をきれいにまとめるために、そこに振り落とされていったものがあるんだな、と。『平家物語』にしても原作にもあるとおり覚一本が書かれて、それは残っているけれども、そこからあぶれたものがある。
そのいっぽうで、最初に原作を持って来られたアスミック(・エース)の竹内(文恵)さんが「この時代のポップスターを描いてほしい」とおっしゃっていたのが面白くて。そこにはグラムロックなどのミュージシャンの画像も添えられていて、自分のなかですぐにデヴィッド・ボウイが歌っているようなイメージが浮かんできたんです。よく「オーパーツ」なんてことが言われますが、その時代に作れるわけのないものが実際に存在していて、ということはそれを作った人がいたんですよね。自分たちが過去を想像するときに、やっぱり矮小化してしまっているところがあるんだと思います。
全然関係ないですけど、小さいころに福岡から知り合いの東京のおばさんのうちに遊びに行ったら「チーズケーキを食べなさい。福岡にチーズケーキある?」と言われて(笑)。東京から地方に行くにつれて文化がどんどん細くなっているイメージで喋っておられるんだなと思ったときに、それが歴史を想像するのにもちょっと似ているような気がして。だから、いま想像できるものは当時も誰かが想像しただろうという自分が以前から思っていた感覚もふまえて、こういう人たちがいたかもしれない、こういうことがあったかもしれないと想像しながら描くことにはすごく意義があると思うんです。
古川 結局、僕らが知っている歴史って全部有名人の話なんですよ。有名人ってだいたい勝った人で。平家は負け組だけど、なんで『平家物語』が残っているかというと、勝った源氏に対して「誰に勝ったの?」ということで存在している。歴史はそういう、ある意味勝った人とか有名な人しか残さないんだけど、一〇〇〇万人のうちのだいたい九九九万人くらいは「そうじゃないほう」で。自分もそっち側の人間として「その『消えていくもの』を『残す』にはどうしたらいいんだろう」と考えると、小説を書けばいいんだな、と。それで、自分を託せる人間が室町時代の真ん中ごろにいたんですよね。
最初は世阿弥の『風姿花伝』の注釈にまず「犬王」という名前が出てきたんですよ。その後に『申楽談儀』の中でも語られているけど、その犬王の演目はどこにも残っていない。それでも、そうやって消えていく、歴史にならないものの側にしか自分は立っていないし、そういう時代でしか呼吸していない。だから「消えていくもの」の側から書けば、そんな宿命を持っている「時代」というものが立ち上がってくるんじゃないかなと思ったんです。大昔という意味での歴史小説を書こうとは実は全然思っていなくて、結局自分を託せて、自分の呼吸している時代を炙り出せるものは何かと考えて書いたことなんです。
湯浅 どういうところで犬王に自分の思いを託せそうだと思ったんですか?
古川 まずは体ひとつなところですよね。体ひとつで物語も作るし、動くし、踊る。僕は二十代まで演劇をやっていて、脚本も書いていたので、そこでまずリンクさせられたんです。犬王は史実でも十代後半ぐらいから曲を作っていたんだけれど、自分も十七歳ぐらいで舞台を一本作れたかと考えると、作れていたんですよね。そのころ聴いていた音楽はいわゆるニュー・ウェイヴとかポジティヴ・パンクで。バウハウスの「ダーク・エントリーズ」って曲があるんですけど、それが最後に流れるような、絶対に誰にも気づかれないような小説を書いてみようと思って。そういう思いを裏側に隠し持っておけば、たぶん犬王は完全に十七歳の日出男くんを投影したまま滅びていけるんじゃないかなと。いま五十代半ばになって、もちろん全然権力にも太刀打ちできなくて何もできないなと思っているんですけど、とりあえず十七歳ぐらいでもそれに突き進んでいく犬王を書ければ、まだ死ぬまであがけるかなと思ったんです。
湯浅 自分がやる気を持続させるためにも、そういう犬王のような前例があるとわかりやすいということですね。
古川 というか、初期衝動に戻りたかったというのがありますね。小説家としてキャリアを積んでいくうちにだんだんとキツくなってきて、それこそ松本大洋さんの『東京ヒゴロ』を読んでいるとズキズキと刺さってくるんですけど、ああいう感じで「俺って何作りたかったのかな」というときに、託せる者がいた。どうやら誰もまだ発見していないみたいなので「もらった!」と思って進んでいったんです。
湯浅 なるほど。犬王はすごく明るいところがいいですよね。このころの時代劇とかを見ていると、本当に謀略、謀略で、疲れるんです。犬王は生い立ちからしてつらいことがたくさんあるんですが、そこに復讐するのではなく「自分は舞台に立って踊りたいんだ」とまっすぐ突き進んでいくところが良くて、僕もこういう人になりたいなあと思いました。
古川 そこはアニメにしてもらったことで「こういう自分がこれまで書いたことがないキャラクターに助けてもらおうとしてたんだな」と、執筆時の自分の姿をもう一回振り返られたところです。
湯浅 長くやっていると、わからなくなってくるものなんですか?
古川 なってきますね。小説はひとりでやっているものなので。たとえば、いま世の中にいる「作家になりたい」という人を全員連れてきても、きっと処女作から三作目までぐらいしか具体的には構想してないしイメージできるってこともないし、けっこう四作目を書かずに満足してシーンから消えちゃうと思うんですよ。「そんなのアホらしい」と思って二十作ぐらい書いたんですけど、そうなったらなったで「俺は工場じゃないよな」という、今度はまた別な気持ちが出てくる。ただ喜んで作っていた時期があったはずだし、喜んで作りたかったはずなのに……というのが、いま湯浅さんが言ってくれた「犬王は喜んで踊って舞台作ってるだけじゃん」というところに委ねていた、託していた思いなんですね。
犬王=『ピンポン』のペコ?
湯浅 あと、古川さんが書かれたのは犬王の物語であるんですけど、それを友魚の視点から見てもいますよね。で、意外と犬王の内面は描かれていなくて。エピローグも最初に読んだときはよく意味がわからなかったんですけど、あれによって話が現代に繫がってくるんですよね。能や琵琶の演奏のように過去にあった人を呼び出して癒すというか、それによって同時にいま生きている周りの人たちのことを思いやれるようにもなる。友魚はたぶんうまく生きられなかったのでああいうふうになったし、犬王はわりと我慢できるというか、友達のためなら諦められる、それでも明るくいられる人だったんだろうな。友魚は後の時代には名も残らなかったけど、同じ時代に理解してくれる人がいてくれたのが良かったと思います。犬王はひとりでも変わらなかったかもしれないけれど、友魚の力を貸してもらってのぼりつめていったし、そんな犬王と出会ったことで友魚もあんなふうに生きることができた。
古川 ただ、役者は役が書かれているからすごい演技ができるし、友魚の場合は犬王という素材があるから、それを曲にして歌うことができたんですよね。犬王の場合は、生まれながらにして与えられている巨大な悲劇的境遇があって、その器のなかでどれだけ遊べるかなんです。「もう俺の設定は用意されているから」というところで演じきる、踊りきる。お互いを支え合っているんだと思います。犬王の明るさということでいえば、特に映画を観て思ったのが、湯浅さんと(松本)大洋さんが組まれた『ピンポン』のペコなんだと思ったんですよ。
湯浅 ああ、そんな感じですね。
古川 一番そのまんまやっていて「内面はどうなってるの? もしかして内面
も表面そのままなの?」という。そう
いう稀有なキャラクターとして、もう
一回立ち上がってきたような気がしますね。
湯浅 ペコもそうですけど、普通の人にはちょっとわかりにくくても、本人からするとたぶんすごくシンプルな考え方をしているだけなんですよね。
古川 あと、犬王はアヴちゃんが声と歌をやってくれたおかげで説得力がすごく増していますよね。もう「そういう人ですから」という感じで(笑)。
湯浅 そうですよね。アヴちゃんは歌詞を練ってもらうときに「なんで犬王のこと、平家のことばっかり歌ってるんだ。かっこ悪い。もっと歌ってる本人の主張を入れたい」と言っていて。そうすると「あ、なんでだろう?」と自分も考えて。でもそれが結局、能とか琵琶ということで、自分のことを語るのではなくて、他人のことを語る人たちということなのかな、と。それによって最後に亡霊たちが、自分たちのことばかりではなくて、あなたたちのことをちゃんと見せてあげたいと思うのかな、と。アヴちゃんもそれを聞いて納得していました。そのぶん、ひとりで呟き唄うところにアヴちゃんの考える犬王の気持ちを出せるといいね、という感じで歌詞を作ってもらいました。