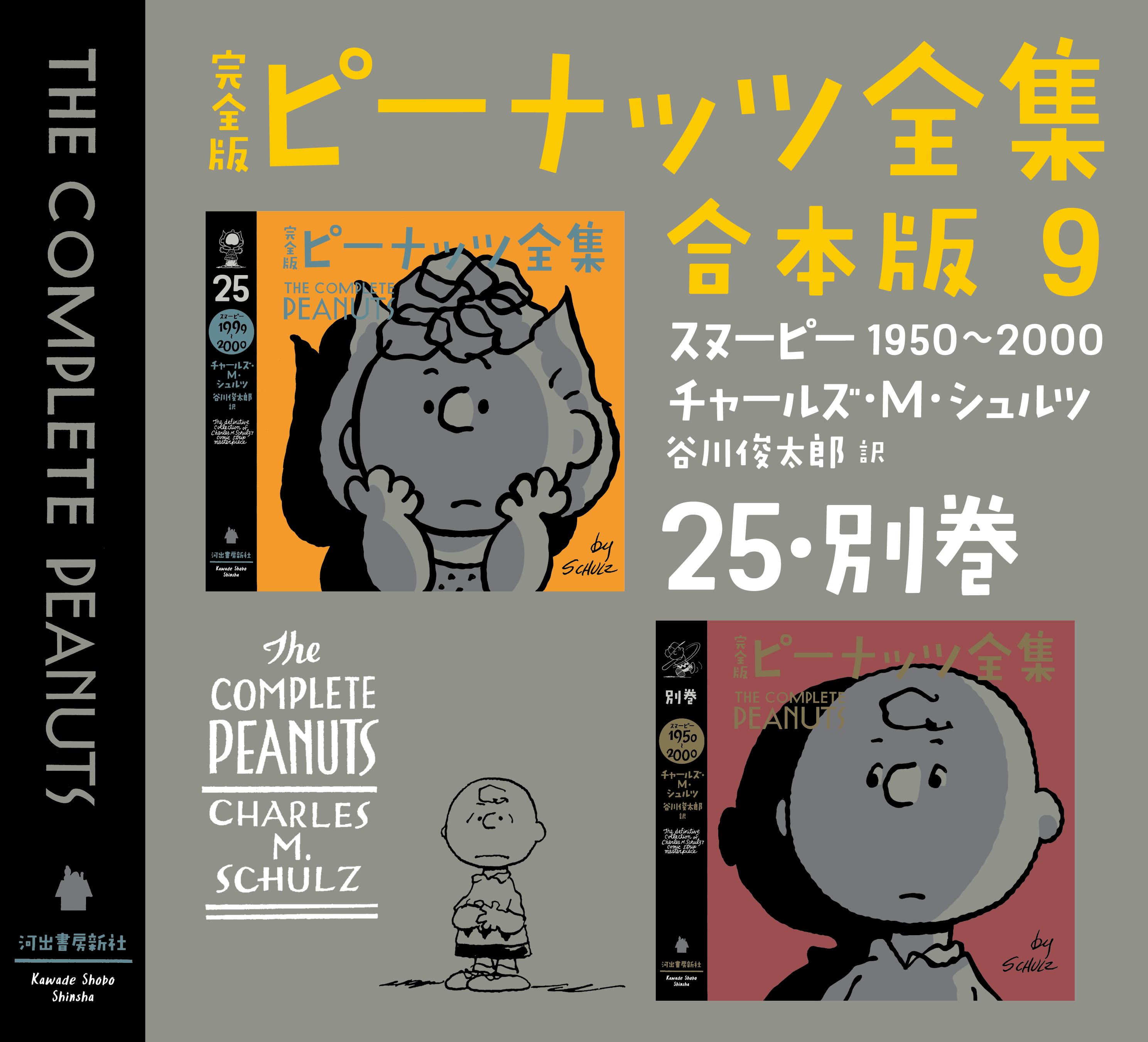単行本 - 外国文学
神話の原点への遡行。『ブロの道』ウラジーミル・ソローキン
ウラジーミル・ソローキン
2016.09.02
〈氷三部作〉完結記念!いろいろ公開中!
『氷』試し読み
『氷』訳者あとがき
『ブロの道』試し読み
——————————-

『ブロの道』
ウラジーミル・ソローキン 著
松下 隆志 訳
訳者あとがき
———————-
神話の原点への遡行
二〇〇二年、現代ロシア作家ウラジーミル・ソローキンは自身の創作のターニングポイントとなる長編『氷』を発表した。「失われた魂の楽園探し」と銘打たれたこの作品は、当初単独の作品として構想されていた。しかしその後、作品の主題はまだ完結していないと考えた作者は続編を書くことを決意し、『氷』という一つの長編は『氷三部作』という一大叙事詩へと発展した。本書『ブロの道』《Путь Бро》(二〇〇四)は、三部作全体の時系列では一番目になるが、執筆順では二番目になる。邦訳は執筆順に『氷』→『ブロの道』→『23000』の順で刊行しており、このあとがきも『氷』の内容を踏まえて書いているが、無論本書から読み進めていただいても一向に構わない。
『氷』が複数のスタイルで書かれた作品であったのに対し、『ブロの道』は全編語り手であるブロ(アレクサンドル・スネギリョフ)による自伝的内容となっている。その意味では『氷』第二部の拡大版とも言えるが、フラムの文体が軽快で感覚的なものだったのに対し、ブロの文体は息が長く、重厚で分析的なものになっている。
シベリアで謎の大爆発が起こった一九〇八年六月三十日、アレクサンドルは裕福な製糖工場主の家庭に生を受ける。ロシアとウクライナにある領地で家族や大勢の親戚に囲まれながら幸福な幼年時代を送るが、第一次世界大戦やロシア革命、それに伴う国内戦による混乱が彼から家族を奪い去る。数年間放浪生活を送った後、アレクサンドルは伯母がいるペトログラード(サンクトペテルブルグの旧称)に戻り、苦しい生活の中で大学に通うが、伯母が政治警察に逮捕され、自身も大学から除籍される。窮地に陥ったアレクサンドルは隕石学に興味を持つ大学の友人マーシャの紹介で、シベリアに落下したとされる「ツングース隕石」を探す探検隊に同行することになる。針葉樹林帯での長く過酷な旅の途中、アレクサンドルは精神に変調を来す。彼は探検隊の住居に火を放ち、高鳴る心臓の鼓動に導かれるように死のタイガをさまよい、そして沼に沈んだ神秘の氷を発見する。隕石の正体は巨大な氷の塊であり、その超自然的な力でアレクサンドルの心臓=心は目覚め、「ブロ」という真の名を語る。そして彼は二万三千人の兄弟姉妹を見つけ、地球を消し去って自分たちの本来の姿である「原初の光」に戻るという使命を果たすため、再び人間たちの世界へ戻る。
『ブロの道』の内容はすでに『氷』で語られていたものが多いが、「心臓の磁石」という新たな要素が追加されている。これは、最初に覚醒した兄弟ブロが二番目に覚醒した姉妹フェルと一緒にいることで、二人の心臓が磁石のように作用し、眠れる仲間を百発百中で見つけ出すことができるという至極便利な能力だ。しかし、その代償として二人は異常な速さで老化し、後継者探しが急務となる。物語の結末ではその後継者の一人が姉妹フラムであり、彼女にももう一人の片割れがいることが示唆されるが、これは『氷』よりもむしろ完結編の『23000』へ繋がる伏線となっている。
さらに、ブロが世界を「心臓で見る」能力を習得して以降の文体の変化は圧巻だ。人間は「肉機械」、鉄道や飛行機は「鉄機械」、住居は「石洞窟」、爆弾は「鉄卵」などという風に、複雑に見える人間世界の営みは次々にプリミティブな表現に置き換えられていく(逆に、作家は「数千枚の紙片を文字の組み合わせで覆うために創られた」機械、銃は「熱い金属を吐き出す鉄管」などと、簡単な言葉が極端に長くなる場合もある)。こうした還元主義的な「異化」の手法はソローキンの初期長編『ロマン』などに通じるものであるが、本書では文体の変化が物語に有機的に組み込まれている点が異なる。
文体の変化に伴ってはっきりと示されていないので補足しておくと、ナチス政権下のドイツに移住したブロたちが潜入する二つの大集会とは、ニュルンベルクで行われたナチスの第六回党大会(一九三四年)とベルリン・オリンピック(一九三六年)のことである。どちらにも登場する「白布の影を作る女肉機械」は映画監督レニ・リーフェンシュタールで、彼女はこの二つの大イベントから『意志の勝利』と『オリンピア』という映画史に残るドキュメンタリー映画を生み出した。
作者の「心」をめぐる論争
『氷三部作』で「心」への回帰を宣言したことで、ソローキンはそれまでなら考えられなかったような論争に巻き込まれることになった。発端は、批評家ワシーリー・シェフツォフがインターネット雑誌「トポス」に掲載した『ブロの道』に対する書評と、それに関連する別の批評家との公開書簡である。その趣旨は、『ブロの道』にロシアの伝統的な古典文学への回帰が見られることを批判的に指摘するものであったが、それに対して今度はソローキン本人が同誌でインタビューに応じ、「まるでベリンスキーとドブロリューボフの文通だ」(ともに十九世紀ロシアの文芸批評家)などとコメントし、『氷』は「いつもと異なる方面から自分たちを見るという直感的な試みの一つに過ぎない」と述べた。
これを受け、シェフツォフは「独立新聞」でさらなる反論を行った。ソローキンの言うことを信じるならば、『氷』は「形而上学小説」だという作者の定義の真剣さは疑わしくなる。まるで劇場のように、ソローキンは覚え込んだ「役割」を演じているだけなのではないか。
このような再批判に対して、ソローキンは「我が罪なりや?」と題する、作家にとっては異例となる長いエッセイを同紙に寄せ、テクストを通してのみ世界を見、「世界のすべてはテクストだ」などと豪語する批評家や学者の姿勢を批判した。その際、ソローキンの反論の矛先は、直接の批判者であるシェフツォフだけでなく、『ブロの道』を「文学に意外さを期待する社会の趣味への平手打ち」と評した文学者イーゴリ・スミルノフにも向けられ、自分が『ブロの道』に取り掛かったのは「何もわざわざ〈退屈に、情報を与えずに〉書いて、消費社会を嘲笑するためだけじゃないんだ」と書いている。
続けてソローキンは、コンセプチュアリズムの影響が色濃い『ロマン』を書いたのは二十年も前の話で、時代の変化とともに作家自身も変化する以上、二十年前と同じものは書かないのだと言う。彼にとって『氷』は依然として「形而上学小説」であるが、あくまで問いを提起するだけで、何らかの解答を与えるものではない。この三部作は「ホモ・サピエンスについて、人々の完全な絶縁状態について、存在と時間について、苦しみの中にあるユートピア的幸福について語り合う試み」なのだ。
ソローキンが自身の作品で「救済」のテーマを扱ったのは『氷三部作』が初めてではない。初期長編『マリーナの三十番目の恋』(一九八二〜一九八四)では、ソ連社会で道徳的に堕落した若い女性マリーナが共産主義イデオロギーによって更生する過程をコンセプチュアルに描いた。ソローキンはこの作品について、主人公のマリーナが「個性から〈解放〉され、無個性の〈集団〉に加わる」ことを「救済」と語っていたが、当時であれば、作者の「心」をめぐる論争が発生することなど考えられなかっただろう。なぜなら、「テクストは紙の上の文字に過ぎない」のだから。『氷』のインタビューでソローキンはコンセプチュアリズムとの「訣別」を宣言したが、それは結果として「作者の死」というポストモダン文学の前提を揺さぶることになったのだ。
ツングース隕石
さて、ここで『氷三部作』において重要な役割を果たしているツングース隕石について紹介しておこう。
二〇一三年二月、ロシア中西部の州チェリャビンスクの上空に隕石が飛来したことは記憶に新しい。多数の目撃者がスマートフォンや車載カメラで落下する火球の姿を捉えていたことから世界的な事件となったが、このときニュースなどで頻繁に引き合いに出されたのがまさに、百年以上前にシベリアのタイガに落下したとされるツングース隕石だった。本書でも述べられている通り、一九〇八年六月三十日、シベリアの小民族であるエヴェンキたちは太陽に似た火の玉を目撃し、大爆発に伴う閃光や轟音、地震を体験した。シベリアのみならず、ロシアやヨーロッパにおいても大気の異常な発光が観測された。
もちろん当時はビデオカメラもスマートフォンもない時代であり、この怪現象は様々な憶測を呼んだ。隕石の正体の解明に取り憑かれたのが、レオニード・クリーク(邦文献では「クーリック」とも。なお、本書に登場するクリークは父称が異なっている)という名の若き隕石学者であった。彼は科学アカデミーの支持と政府からの資金援助を受け、一九二一年、初の隕石探検隊を組織した。調査の結果、彼は隕石がシベリア中部を流れるエニセイ川の支流であるポドカメンナヤ・ツングースカ川の流域に落下したことを特定した。その後も一九二七年から三九年にかけて数度の探検を行ったが、大規模な森林倒伏やクレーターなど隕石落下の痕跡らしきものを発見しただけで、隕石そのものの発見という悲願が実ることはなかった。
探検は第二次世界大戦によって中断され、戦後、ツングース隕石に対する興味は科学者から小説家に移った。一九四六年、SF作家アレクサンドル・カザンツェフは『爆発』と題する短編を発表し、その中で一九〇八年六月三十日の爆発は隕石ではなく、異星からやって来た原子力宇宙船の着陸失敗によって起きたとする仮説を提示した。
もちろん、カザンツェフの仮説は科学者からは大いに批判されることとなったが、一般市民の間では好評を博した。以降もツングースの爆発については、核爆発説、彗星説、宇宙塵説、宇宙人説、反物質説、レーザー光線説、ガス噴出説、等々、現実味のありそうなものからオカルト的なものまで様々な仮説が提出された。本書との関連で興味深いのは彗星説である。この説によれば、彗星の核となっていたのは、様々な粒子と凍結したガスが混ざり合った氷状の物質だという。だとすれば、ソローキンの仮説もあながち無根拠なものではないのかもしれない。もっとも、近年の研究(二〇一三年)によると、ウクライナ・ドイツ・アメリカの科学者グループらが爆発の原因が隕石だったことを特定したとされる。
科学的な真実はともかく、カザンツェフやソローキンの他にも、スタニスワフ・レム『金星応答なし』(一九五一年)、ストルガツキー兄弟『月曜日は土曜日に始まる』(一九六五年)、最近のものではトマス・ピンチョン『逆光』(二〇〇六年)、ポーランドのSF作家ヤツェク・ドゥカイ『氷』(二〇〇七年)など、文学の世界では今なおツングース隕石の謎に対する数々の刺激的な解釈が試みられているので、関連する本を渉猟してみるのも一興だろう。
ちなみに、日本でもツングース隕石を題材にした読み物がいくつか出版されており、SF漫画家の星野之宣による短編『はるかなる朝』(一九七五年)や、『ノストラダムスの大予言』(一九七三年)で知られるルポライター五島勉による『ツングース恐怖の黙示』(一九七七年)などがある。邦訳書としては、ロシアの地質学者ボリス・ウロンスキーがクリークの足跡を丹念に追った『ツングース隕石の謎』(一九七一年)があり、本書のシベリア探検の記述はしばしばこの本に依拠している。
また、こうしたツングース隕石にまつわる一連の言説をまとめたものとして、越野剛「ツングース事件の謎」(『天空のミステリー』所収、二〇一二年)があり、あとがきを書くに当たって参照させていただいたことを付記しておく。
———————