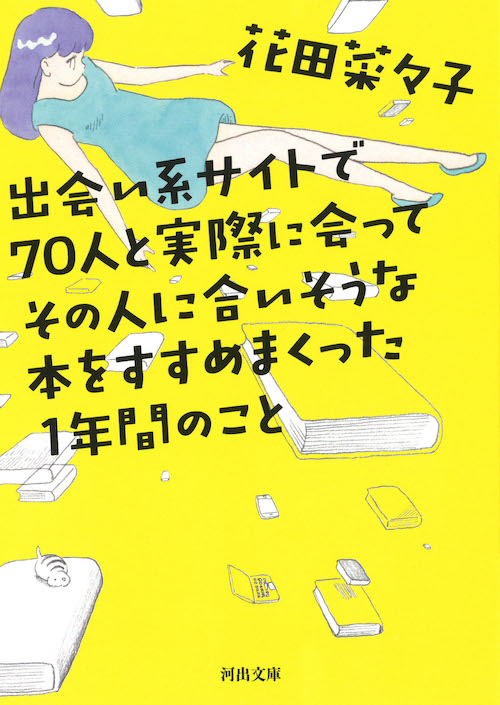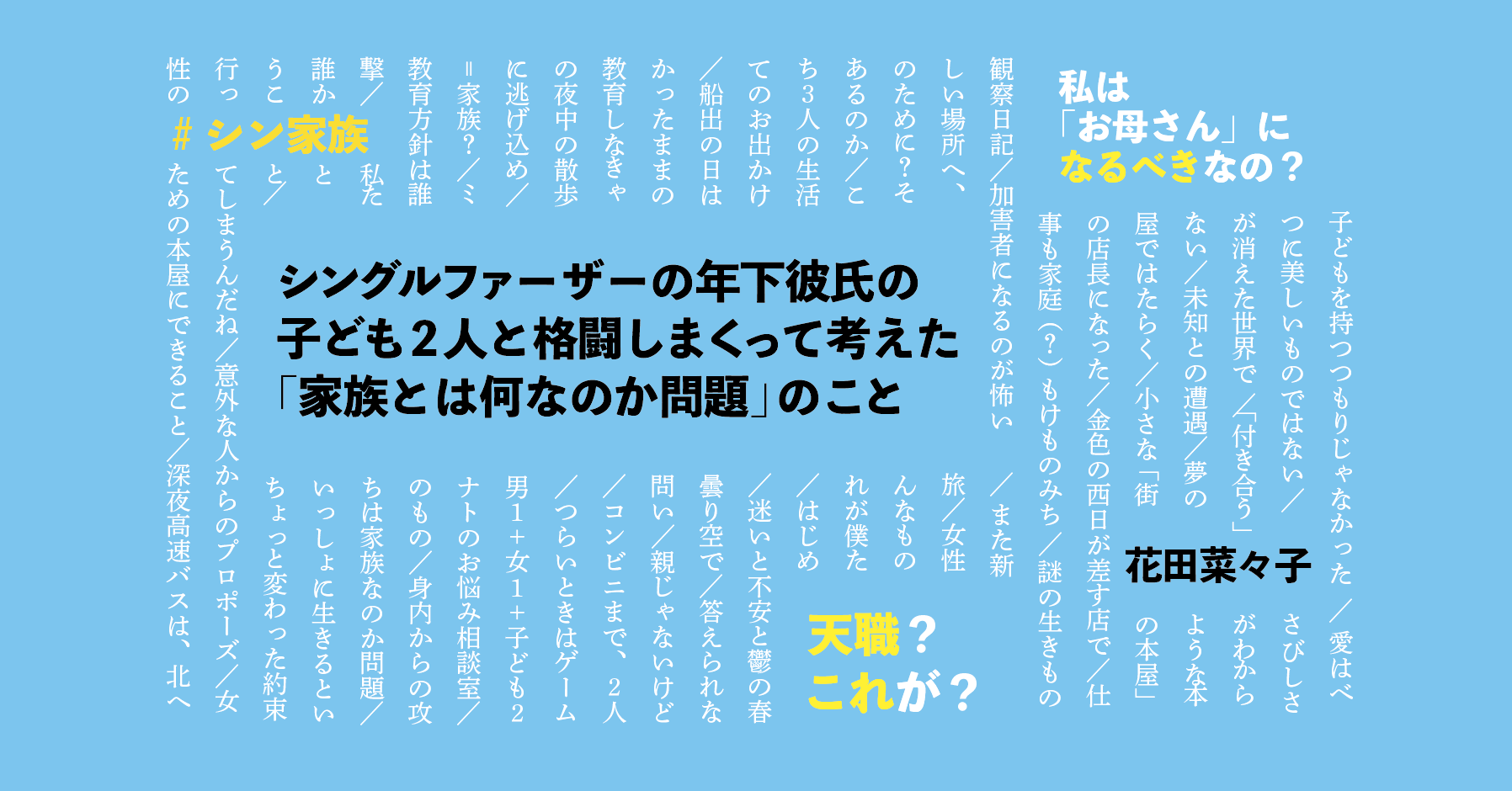
単行本 - 日本文学
「仕事も家庭(?)もけものみち」!【試し読み】第3章『シングルファーザーの年下彼氏の 子ども2人と格闘しまくって考えた 「家族とは何なのか問題」のこと』 - 2ページ目
花田菜々子
2020.03.05
加害者になるのが怖い
しかし、「ちんこ」という単語を聞いていっしょに笑っているくらいはいいのだけど、困るのはお風呂上がりのマルちゃんが裸でリビングに突入してきて、ちんこを見せてこようとすることだった。その頃アキラ100%という芸人がよくテレビに出ていたのだが、その真似をしてバスタオルをぐしゃぐしゃに股間にあてて隠して登場しつつ、踊りながら手で交互に持ち替えてこちらににじり寄ってくるのだった。
さすがにどう対応したものか。というのは、私は小学2年生の男子のちんこを見てもさすがに性的には認識しない。けれど、私が「外から来た女の人」という存在であるならば、そういうものを見せたりしてはいけないよ、ということを教えなければならないはずだ。だが、もし「お母さん的な存在」であるならば、子どものちんこなど見て当然なわけだけど……。見てほしいのだろうか? なんで? そういう距離を測ってる?
いや、問題はもっとシンプルで、マルちゃんはエンターテイナーだから、きっとあらゆる手段を使って私を笑わせたいだけなのだ。だとすればこの場での正しい対応って何? それは教育の本に書いてあるような正しさではなく、お笑い的な正しさなのか? 私は何のマニュアルを根拠にしたらいいのだろうか?
それに、見るのを嫌がる(きゃーやめてー的な)アクションをする、しかしそれは本気で嫌がってはいないということをきちんと表現する、それに対してマルちゃんがさらに見せようとする……という笑いの構造を定着させるというのは、フェミニスト的な観点からすればいかがなものだろうか? だって時代は“No means no”(性的な誘いになどに対してダメと言ったらダメ)だし……。しかし、フェミ的な行動原理を優先して「そういうことはダメだよ」と言うのもちょっと違うような……。うーん。はて。
結局「や、やめてくださいよー」と言いながら手で顔を覆いつつ、ときどきちらっと確認する、というアクションを選択し、マルちゃんも踊りながら「あ! いま見た!」「見てない」「見た!」「見てない」というやりとりで双方のメンツ(?)を保って収めたのだが、これがはたしてベストの選択なのかはわからない。
いったい何が正解なのか。
異性の子どもだから気にしないといけないことがある。彼らの身体にまつわることだ。
ちんことうんこに関しては異常なほどの愛と執着を見せるけれど、女性をネタにするエロというものにははっきりとした線引きをしており、それらは一切取り扱われなかった。たとえば丸いものがふたつあったらそれを胸にあてておっぱいに見立てる、くらいのことなら彼らが十分にやりそうなことではあったが、なぜかそれはないものとされているようだった。そして彼らは私を「女」だと知っていたので、私に触ろうとすることはなかった。2人とも父親であるトンにはべったりなのでそれは少しさびしいようにも感じたけれど、彼らがそう認識できる年齢になっている以上は、こちらからスキンシップを求めるのは気持ち悪い。
私がいちばん恐れているのは、異性の子どもに対して自分が彼らの親に近い立場から性的加害者になることだ。
私とは逆の立場にある、〈娘を持つシングルマザーと結婚した男の人たち〉に片っ端から聞いて回りたい。
どう捉え、どう行動することでその可能性を回避するようにしたのか。大人の男と子どもの女、という関係性がいちばん問題が発生しやすいと思うのだけど。というか、子どもが小学校の高学年とかになったら、知らないおじさんが家にいることを「なんか嫌だな」と思うことのほうが当然な気がするし、そこをどうやって超えて、どうやって意識しないように意識していくんだろう。私の考えすぎなのかな。もっと自然でいられたらいいのにといつも思う。
けれど、血がつながっていたらいいのだろうか? という疑問も同時にある。父親の娘に対するセクハラなどはもちろん許されるものではないと思うが、SNSで自分の息子を「私の小さな彼氏でーす」と言ってハートのスタンプがいっぱいのツーショット写真を公開したり、小さな男児に「ママにチューして」などと平然と言う女の人たち。以前はそれほど気にもしていなかった彼女たちの言動が急に気になるようになった。自己防衛なのかもしれないが、嫌悪感がわく。血がつながっていたら鈍感でいても許されるのだからいいよね、という、自分の複雑な羨みなのかもしれない。その人たちの子どもは喜んでいるのかもしれないし……他人の家のことはわからないけど。
けれど日が経つにつれて、マルちゃんは私とトンが並んで座っているあいだに無理やり入り込んできたり、「これおいしいから食べて」と無理やりに口に直接グミを突っ込んできたりするので、なるほど、接触すること自体は嫌ではないらしい、ということを知る。そのうちに、慣れてくるとコンビニを走り回るマルちゃんの両脇をホールドして止めたりすることはできるようになった。
だが、行き過ぎてしまうこともある。コンビニの帰り道、マルちゃんがトンに「たまにはおんぶしてよ」と言って、トンはしばらくおんぶしながら歩いていたが「はあ、重い」と言い始めたので「代わろうか?」と訊いてみた。「お、いいね、お願いしよう」とトンに降ろされたマルちゃんの近くにしゃがんでスタンバイするが、マルちゃんはちょっと考えて言った。
「いいよ……なんか恥ずかしい!」
そう言われて、たしかに調子に乗りすぎたかも、と反省する。気をつけよう。
一方、ミナトに関してはマルちゃんよりはガードが固いしもう5年生だし、ということで、オールNGの方針でいたが、ある日のこと、
「この服くさい! 麻雀マットと同じにおいする!」
と自分の着ているTシャツを引っぱって嗅ぎながらトンに嗅がせていた。
「うん、たしかにくさいな。洗ったのになあ」
「これ洗ってもいつもくさいんだよ」
「俺も嗅ぐ!」
マルちゃんが嗅ぎに行って、「くせっ、くせっ」と手を叩いて喜んでいる。
こういうときは外野になって笑って見ているのが自分の役目だ……と遠巻きに見ていると、ミナトが自分のところまでTシャツを引っぱりながらやってきた。
「はい」
「え、私も嗅ぐの?」
「うん」
ミナトはそれは私にはさせないだろうなと思っていたので意外だった。驚きを見せないようにして、なるべく普通にTシャツに鼻を近づける。
「わ、なんか変なにおい!」
「でしょ? ほら、やっぱりくさい」
なぜかくさいことがうれしいらしく飛び跳ねていた。
子どもとのベストの距離はどれくらい? というのはこちらで決められるはずがなくて、こうやってそれぞれのスピードとバランスで、どこまでなら侵入してもよい、というラインを彼らが決めて教えてくれるようだ。
関係性は無理やりひとつの方向を目指してこじ開けていくことじゃない。日々のやりとりの中で薄い紙を一枚ずつ積み重ねるようにして、オリジナルの形を作っていくもののようだ。
また新しい場所へ、旅
その頃、また別の事件が起ころうとしていた。
昔からの出版業界の知り合いで、年は離れていたけど友人のように親しくさせてもらっている人から、ある日突然連絡が来た。
「今度女性向けの本屋を始めるっていうプロジェクトに関わってるんだけど、花田さん、相談に乗ってくれない?」
「女性向けの本屋? へえー、なんか大変そう」
相談というのは、肝心の店長をやる人が見つかっていないまま、あと半年で新店をオープンすることだけが決まっているので、誰か店長をやってくれそうな人を紹介してほしい、それとオープン時の選書を手伝ってほしい、という内容だった。
「花田さんが店長で来てくれたらいちばんいいけど……それは無理でしょう?」
「そうだね、さすがに……。まだパン屋の本屋も1年経ってないからなあ」
「うん、まあそれはそうだと思うんだ。だからとりあえずオープンに間に合うように本を選んでもらえないかなあ、もちろんきちんと見合った額をお支払いするから」
「選ぶっていっても……ちょっと仕事量が多そうで、片手間でできるかどうか。それに私、実は本を出すことになりそうなんだ。ちょっと忙しいかも」
「えっ、そうなの?」
この頃、少し前にやっていた、出会い系サイトで出会った人に本をすすめてきた経験をウェブマガジンで書いた文章がバズって書籍化することが決まり、ちょっと慌ただしくなっていた。そんなことに関わっている場合ではない、という気持ちもあった。
「誰か社内にできる人はいないの? 新しく店長になる人か、会社の中にいる人が選んで、オープン後も同じ人が売り場づくりを進めるのがいちばんいいと思うんだけど」
「それができるならそうしてるよ。『できる人が誰もいない』ってことだけはプロジェクトの意見として一致してるんだ」
そこで店長ができそうな書店員の友人何人かに声をかけてみたが、タイミングが悪かったり、企業の中での仕事というところに興味を持ってもらえなかったりして、私の知り合いではどうにかなりそうになかった。絶対、どこかにやりたい人はいるはずなのになあ。適任な人も、書店業界のどこかにいるはずなのに。
さらにプロジェクトの人たちと会ったりして話を聞けば聞くほど、「このままではやばい」ことがひしひしと伝わった。内装・店舗名・ロゴ、外側だけがどんどん固まっていって、内側が空洞だ。もちろん自分が責任を感じなければいけない話ではなかったが。
自分がこの店に何の本も選ばなくても、誰かがオープン前までに棚を埋めるだろう。「女性向けの本屋」。それはすごくナイーブなテーマだ。「女性向け」を謳いながら女性のことなんて1ミリも考えていないようなハリボテの企画はそこらじゅうに溢れている。
美容の本やファッションの本、女性向け自己啓発の本をたくさん揃えて、なんとなくの女性らしさを作ることはできるだろう。だが、そんな本屋ができてしまうかもしれないことを、私はいち書店員として見過ごしていいのか? せっかく150坪の広さと莫大な予算をかけて、そんな店が誕生してもいいのか?
「あの、やっぱり私が店長をやるって、アリですか?」
やめとけ、それ以上首を突っ込むなよ、という心の声をさえぎって、思い切って聞いてみる。
「え? もちろんそれは、そうなったらすべて解決するけど、だって、花田さんは……」
「ちょっと考えさせてください。一週間ください」
もちろん正義感や使命感だけではない。打算とまではいかないが、自分のことを考えていた。
出会い系の本の原稿を書き進める時間が必要なことや、穏やかな暮らしのことを考えると、このまま今の職場に残ったほうがいい。いま転職なんてしたら原稿どころじゃなくなる。という思いと同時に、パン屋の本屋は取材NGにしていたので、店のことではないとしても、本を出すことでメディアに私が露出するのを嫌がるだろうな、という心配が心の片隅にあった。
せめてあと2年後にこの話が来てくれたなら。そう思ったが、2年後ならよくて、今はだめなのか? その基準は何なのか? それに2年後に同じ話があるはずはない。
ここは居心地がいい。でもまだ私は自分の人生の終着点をここに決められない。どんどんどこかに行きたいという気持ちも湧いている。
それに新しい本屋の逆境っぷりにも正直ワクワクしていた。だってどう考えても無理ゲーだ。スケジュール的にも大変だし、女性向けの店というコンセプトで150坪は無謀に思える。行ったら大変なことになるだろう。そう思うとかえって行きたくなる。どうかしているのだが。
逆境好きじゃん。行っちゃえよ! と心の外野がうるさい。
パン屋の本屋では、店の品揃えや接客についてはほとんどオーナーから何かを言われることはなく、まるで自分の城のようにやりたい放題に好きに本を選び、並べていた。それは自分にとってもタダで手に入った自分の城のようで、自由にやらせてくれるオーナーの信頼はほんとうにありがたかったし、どう考えても人から見たらうらやましい状況なんだろうと思った。でも、実際はそこに未練はなかった。そして好きな音楽をかけてすごすお客さんの来ない雨の夜の美しい時間も、好きな本をのんびり読める時間も、惜しいようでいて惜しくはなかった。
でも、最後まで、ひとつだけ自分を強く引き止めるものがあった。
強く後ろ髪を引かれ、最後まで悩み、苦しく思ったのは常連のお客さん、具体的に、あの人とあの人とあの人とあの人と……もう会えなくなる、あの、少しだけ会話をかわすような、定期的にちょっと会えることを日々のささやかな楽しみにできるような関係が、すべて失われてしまう、ということだった。いくらなんでも別れのときが早すぎる。でも、それが嫌ならこのままここを辞めなければいいだけだ。でも……。
引き裂かれるような気持ちだった。
そんな迷いの日々の中で、私の週1の休日に店に立ってくれているアルバイトのさちこが、私がレジに立っている日に店に遊びに来た。
「自転車を買ったんですよ! かわいくないですか?」
外には真新しい、ベージュに塗装されたおしゃれなデザインの自転車が止まっていた。
月曜日はパン屋が休みのために、本屋に来るお客さんも少ない。自転車に乗れない、というさちこが店の前で練習をするのを、中庭に出て眺める。心地よい秋の風が吹いていた。さちこがよろよろとした運転で何度も店の前を往復する。こんな幸せなのんびりした時間の中に、いつまでもいたかった。こんな決め切れない2択の前に立ち尽くしてしまうとき、私にはいつも無意識に思い出してしまう1冊の本があった。いや、その中のひとつのフレーズというべきか。
それは、岡本太郎の『自分の中に毒を持て』という本だ。
芸術家として生きた彼の、妥協のない激しい生き方が濃密につまった人生論のような本だった。そこには、2択で迷ったときには必ず「あえて危険なほう、怖いと思うほうを取れ」というメッセージが描かれていた。「ワクワクするほうを選べ」「やりたいことを選べ」はあらゆる自己啓発本に書かれていたことで、ある種聞き慣れていたのだが、怖いほうを選ぶとはどういうことだろう、と消化不良のまま心にずっと残っていた。太郎は「万博にシンボルを作ってほしい」という依頼があったときも迷ったが(たしかにそのオファーをもらって、ワーイとよろこぶような人間ではないだろう)、プロジェクトに参加することのほうが「怖い」と感じたので決めた、と書いていた。このエピソードと言葉は今もこうして決断をせまられるたびにボディブローのように身体に効いてくる。若い頃に読んだ本の効能はおそろしい。いつしか骨の奥までしみつき、自分のものとなって、自分を決断させてしまうのだから。
もう私の心は決まってしまっていた。こんなにいい店をもう去らなければいけないなんて、なんて馬鹿なんだろう。でも、後悔はない。
こうして私はここを出て行くことに決めた。
女性のために? そんなものあるのか
女性向けの本屋。女性のための本屋。
「あえて困難なものに挑戦するのが面白い」とか何とか思いながらかっこよく引き受けたのはいいものの、いざ引き受けてみて、何か素晴らしいビジョンやアイデアが思いついているのかというと、べつに何もないのだった。
こういうときは、誰か友人に壁打ちの壁になってもらうのが効果的かもしれない。出版社で働いている女友達を居酒屋に呼び出して泣きつく。
「女性のための本屋、っていうのをやることになったんだけどさ、どう思う? っていうか、まず、どういう本を置いたらいいのかね?」
「女性〜? 恋愛の本とか? あとヨガとかじゃない」
「恋愛、ヨガ……ふんふん、なるほど。ってさ、いや、そういうことじゃないんだよな」
「じゃ、どういうこと?」
「いや、そういうことなのかな? なんか、テーマというか、コンセプト?」
「それが『女性』なんでしょ?」
「女性のための本屋です、って言われて、わー、行きたいな〜って思う?」
「どういう意味? とは思うね。まあでも見には行きたいよ」
「試されてる感……で、女性を馬鹿にしている、とか言われて炎上しちゃうんだ、きっと」
「そこまで悲観しなくても」
「女性のための本屋、って、他にどこかあるのかな?」
「小さいお店だったらあるかもね。あ、クレヨンハウスとか? あれって、どういう感じだっけ?」
「たしかに。骨太な思想ありきな感じ。実際、絵本の品揃えとか重厚で圧倒されたなあ。あとオーガニックな印象」
「ヨガ、オーガニック、自然のままに私らしく生きる……って感じだね。そして野菜を干したりジャムを作ったりするんだよね」
「えー! そういう店? そういう店になるの?」
「知らないよ」
ぐらぐらした話が続くだけで、これだ、という道筋がまったく見えない。
「やっぱり女の人向けの本、っていうので分けるってことに無理があるよね……。そういうエコな暮らしを実践する男の人だっていっぱいいるし、女の人だからこれが好き、なんて共通認識のあるものなんて何にもないんじゃない?」
「パンケーキじゃん?」
「人がまじめに話してるのに!」
「時代はインスタ映えだよ〜」
「まあたしかに、あるけど、でも『女の人が好きそうな』って言葉で考えようとすると、どうしてもそういう発想になっちゃうんだよな。頭が悪そうというかさ。インスタ映えしたい女の人を馬鹿にしたいわけじゃないのに、企業とか店が『ほら、インスタ映えするでしょ?』って先回りして作ってるものって馬鹿にしてる感じがする」
「それはわかってないやつらが女を見下して作った失敗パターンでしょ、ちゃんとやったらいいものになるんじゃないの? 今は食べログよりインスタで店を探す時代なんだから」
「インスタ映えする本屋なんか誰も探してないでしょ?」
「いや、その写真見て『この本屋行きたいな』ってなるんじゃない?」
「まあ……見た目がダサいのは嫌だけどね……要するに中身が伴っていればいいんだよね」
「んー……でもさ、中身がよくてもチェーン系の書店みたいな内装だったらべつに写真は撮らない。中身ねえ……女性のための本屋、というと、フェミニズムの本とかも置くでしょ?」
「そうだね。それは個人的にも取り揃えたいんだけど……私自身も社会学というか、女性差別にかかわらず、障害者とか、LGBTとか、移民や在日外国人の人とか、マイノリティーの人たちの権利が守られて、その人たちがより生きやすくなることに興味があるから、っていうのもあって、そういう本は自然と置けると思うんだけど、そういう主張が強い本ばかりが揃って息苦しくなるのも嫌なんだよね」
「そのへんはバランスが難しそうだね」
「そもそも店が広いから、そういう本だけで揃えるなんて無理だけどね。……って考えたら、逆に『どういう本を置くべきか』って問題じゃなくて、女性に紐づけて置ける本ならどんな本でも置かないと棚が埋まらないんじゃないかって問題のほうが切実かも」
「何坪だっけ?」
「売り場で150」
「って、聞いておきながら坪数で聞いてもわからないや。青山ブックセンターの本店で何坪?」
「わからん。でも同じくらいかもしれない」
「え、めちゃめちゃ広いじゃん」
「だから困るんだよな〜」
「でも実用書で埋まりそうな気もするけどね」
「まあ、さっきの続きじゃないけど、女性といえば、美容、ファッション、あと占いとか、コミックエッセイ、恋愛、結婚、育児、あと、旅行、アート、カフェ、料理、手芸、インテリア、暮らし、占い、ペット……そんな感じかな?」
「文芸はやらないの?」
「あ、やるやる」
「それは女性作家だけ置くの?」
「ね、それがまた悩む……というか答えがない。だってほとんどの女の人は男性作家と女性作家の区別なく読んでるだろうし、女性作家の本しか置かないって決めたら相当つまらない棚になるよね。でも、だとしたらどうやって『女性らしい』文芸の棚を作れるのかわからない……」
「あれ、ビジネス書は?」
「それも悩んでるんだよね」
「新刊配本はあるの?」
「それも悩んでるんだよね」
「何にも決まってないんだね」
「決めるための道しるべみたいなものがないと動けないよね。でも、まずは決めてみて、オープン後の動向に合わせて変えていくしかないのかもなあ」
「超大変そうだね」
「はたして完成するのかな? って他人事みたいに思ってる」
パン屋の本屋の在庫量は約4千冊。それくらいなら手作業で、1タイトル1タイトルを選んでいくだけで埋まるということは実感としてわかっていた。しかし、それにしたって、何かテーマのようなものとか棚の流れみたいなものを考えながら本を4千冊発注することはけっこう大変だった。
それで言うと、その新しい店─「HMV & BOOKS HIBIYA COTTAGE」(コテージ)は、そもそも何冊必要なのか? これも概算でしかないが、標準的な150坪の店ならだいたい4万冊の本が入っているという。4万冊を手作業って、たぶん非現実的なのだ。でもそれ以外にやり方がわからない。おそらくは、取次が「新規開店セット」みたいな本のリストを持っているのかもしれないけれど、それだと「普通の本屋さん」の品揃えになる。
「あ、そうだ。ひとついい情報があったんだ」
「なに?」
「日比谷のその店は宝塚の劇場が近いらしくて、前にそこにあった書店でも、宝塚関係の本はだいぶ売れていたらしい。あと、演劇の劇場も周囲にいくつかあるらしくて、だからそういうものは多めに置こうという話になってるんだ」
「へえ、そうなんだ」
といっても、宝塚のことなんて1ミリも知らないので、品揃えのしようもなく、こちらもまた懸念材料ではあるのだが、まあ、これは詳しい人を見つけられればクリアできそうだ。
「あと、会社のHMVがCD屋さんだから、女性ファンが多いジャニーズとかK─popとかに強いらしいんだよね。だからそういうのを置くのは『女の園』って感じで面白いなあと思ってる」
「女ヲタが集まる店になるんだ」
「うん、そうだねきっと。女ヲタの楽園ってなんだかとってもいい感じだね。あの、今はあんまりないかもしれないけど、昔レンタルビデオの店で、「18禁」ののれんがかかってて、そこは男の人が女の人の目を気にせずにAVを借りられるようになってたよね。オタクであることを恥じる必要はないけど、総合書店ではまわりの目が気になってゆっくり売り場を見られない人が、男性アイドルの写真集をじっくり吟味できるようになったらいいなあ」
「いいねえ、女子高っぽいノリ。……うん、コンセプトはだいぶ固まったんじゃない?」
「そうかな? そうかも?」
「うん、すごい行ってみたい店」
「ほんと? よかった! 助かった」
「お役に立てたならよかったよ」
うんうん、とってもいい感じだぞ、と上機嫌で解散したものの、家に帰って、さあ、プロジェクトの人たちにも伝わるような企画書を作ろう、とパソコンに向かうと急に頭にもやがかかったようになる。
結局どういう店なんだ?
あのときはベラベラと思いつくままにしゃべったけど、「女性の本屋」だから「料理」「手芸」「カフェ」って、すごくステレオタイプな思いつきだし、差別的発想になるのではないか。女性でも「電車」や「戦国武将」や「釣り」が好きな人はいくらでもいるよね。そんなことは知っている。その人たちをいないものとして「女性のための本屋なので料理の本や手芸の本がいっぱいありますよ〜」と宣伝していいものなのか。
それに「女性のための本屋」という区分を、トランスジェンダーの人はどう思うだろうか? 性別に分かれられないことを、排除されているように感じるだろうか? というか、そもそも、男性はどう思うのだろう? 男性がつまらない本屋でもいいのかな。
私はもともとフェミニズムに限らず、子どもの頃から、社会や世間から「〜でなければならない」「〜であるべき」と無意味な習慣や前時代的な考えを押し付けられることが苦手だった。その耐性が著しく低いせいで、普通に学校に行くこともかなりしんどかったし、普通の親が子どもに言うような命令や指示も受け入れることができなくて、ただそこにいるだけで大変だった。そんな自分にとってはフェミニズムの本はたいてい「こうでなければ」の呪いを解いてくれるものであり、新しい考え方を教えてくれるものであり、心を自由にしてくれるものだったので大いに共感していた。
そんな自分が、自分の生き方に沿って選書をすれば、自然と「もっと自由に生きよう、結婚・出産はしてもしなくてもいい。誰かに依存せずに自立して生きていこう」という本ばかりになってしまう。
でも、それでいいのだろうか? それはちょっと違うんじゃないか?
たとえば夫に愛されることを望んでいる人、仕事をせずに家庭を支える生き方を選んだ人のことを責めるような店になってはいけないのではないか。愛されることばかりを目的と盲信して自分を見失い、依存の関係になってしまうことが問題なのであり、愛されたいと願うことは何も間違っていない。
「明日のデートには何を着ていったらいいのかな、どんな服だったらかわいいと思ってもらえるだろう」と考えながらわくわくと本屋に来た人に、
「愛され服などもってのほか! もっと己を持て! そんな媚びた精神の本は一冊残らず燃やしてやったわ!! ワハハ!!」とその心を潰す資格があるのだろうか?
いや、そう発言する人や、そういう店があってもいいと思うのだが、それは、ここでの私の仕事ではない。気がする。わからないけど。
「女性差別とは何か」「私たちは不当に何かを押し付けられているのではないか」という問題を考えたいときに、役に立つ本が揃っている本屋でありたい。
同時に、「難しいことは今日は何も考えたくない。仕事つかれた。ひたすら嫌なことを忘れて、たのしくてやさしいものに出会って癒されたい」というニーズもかなえられるような本屋でありたい。
キラキラした空間にしたい。あれもこれも、手に取りたくなる本ばかりで、来たら元気になれる店。ワクワクするような本がいっぱいの店。自分ももっとこんなふうになりたいな、とか、がんばろうと思える店。
同時に、「キラキラしなければ女として価値が低い」という呪いを植え付ける店にはなりたくない。もともと本の役割は、日陰や暗闇に価値を見出し、そのあり方に寄り添うことがメインみたいなものだ。だから極端な話、ずっとキラキラしていられて、悩みもないなら、本なんて読む必要はないのだ。
……と、理想を掲げるのはかんたんで、考えれば考えるほど自分の理念の崇高さにドヤ感(?)でいっぱいになり胸が熱くなるのだが、そんな形而上学的には可能な店の現実化は可能なのだろうか? 可能なのだろうか? っていうか、今からそれを全部成立させる店のあり方、棚のあり方を全部自分で考えて1冊ずつ発注して並べなきゃいけないのである。無理な気しかしない。
もっと、そういうことじゃなくて、行ったらただ楽しくて、女子的なテンションが上がって、「こういう店は女友達と来るに限るよねー」みたいな、なんだろうな、そういうの、何っぽさといえばいいのだろう、と毎日のように寝ても覚めてもぐるぐる考え続けて、結局「ルミネ的」「ディズニーランド的」というワードが近いのかなあとぼんやり思う。
多分だけど、ルミネに崇高な思想はない。だけどルミネに行くとなんだかテンションが上がる。資本主義的だな、ハリボテだなと感じることもあるけど、それでも、溢れんばかりの洋服の洪水に、うやうやしく飾られたアクセサリーや、新しいメイクブランドのおしゃれなパッケージや、落ち着いて洗練された文具、おいしそうな新製品の輸入菓子、流行のかわいい服を着てやさしく話しかけてくれる店員さん……そんなものに囲まれて、勢いのあるビジュアルとキャッチコピーのポスターに無駄な買い物を肯定してもらって、「女子力」を充電したような気持ちになって帰る。
ルミネに行くとなぜワクワクするのだろう? と考えることは、コテージを考えることに役立ちそうな気がする。
ディズニーランドは、女性だけのためのものではないし、男性にもファンがいると思うけど、基本的には世界観を確固たる意志で構築することによって、楽しさを生み出している。「行列がすごい」とか「高い」とか、ネガティブな要素もあるのに、あそこまで「ここでは幸せに楽しくすごしてね〜」というメッセージが伝わるのはすごい。あんなふうな店になったらいいな。なんか変な帽子をかぶりたくなっちゃうような、おいしくもないポップコーンをつい買いたくなっちゃうようなあの仕組み。
私の中では、なんとなくの店のイメージというのは次第に固まっていった。
もちろんイメージができただけでは棚は1ミリも埋まらないのだが。
これが僕たち3人の生活
パン屋の本屋を退職し、土日に休めるようになると、トンの家で過ごす時間がぐっと増えた。金曜日の夜から行って日曜の夜に帰るという、まるで単身赴任のお父さんスタイルだ。どう進めたらいいかわからない「女の園」づくりの仕事に悩んで帰ってきて待っているものは、どう進めたらいいかわからない「男の園」での自らの身のやつし方だ。
会える時間が長くなると自動的に子どもたちとの親密さは増す。自分の予定があったりして週末に行けなくて1週空いたりしてしまうと、また距離が遠くなってしまっているのではないかと不安になる。けれどたくさん時間を過ごすことで仲良くなろうって、なんだか暴力的でもある。子どもは拒否権がないのだから。よっぽど嫌だったら父親に「もう来ないようにしてほしい」と伝えることもできるかもしれないが……。
でもある日、撮っていた2人の写真を見返したら、ミナトが下を向いたり、顔が映らないようにしている写真が多くてハッとした。いい場面だな、かわいいな、と思って何気なくiPhoneのカメラを向けていたけど、嫌がっていたことにも気づかなかったし、写真を撮らないでほしいとは言い出せなかったのだなあと思うと申し訳なくて、鈍感な自分が嫌になった。嫌だったら言ってくれるはず、言わないんだから大丈夫、ってまるで最近話題になっている性的同意の話でいうところの、加害者の言い分と同じじゃないか。
子どもたちとの関係性は深くなっていくようで、一進一退だ。盛り上がって楽しい時間を過ごせたりたくさん話せたと思うときは弾むような気分で家に帰ったし、子どもたちが冷たいように感じたりなんとなくうまくいってないように感じた週末は、もう来ないほうがいいのかな、どうするのが正解なのかな、と考え込んでしまう。それに、その「うまくいっている」の判定も、結局は私が思い描く「素敵なファミリー」的なイメージの一方的な押し付けじゃないか、と思うとどうしたらいいのかわからなくなる。
自分で自分に問いかける。おまえの目的はなんだ? 子どもと、「仲良くなる」ことか? 子どもに好かれている「素敵な私になる」ことか? 子どもたちを自分の思い通りに動かすことか?
ちがう。純粋に子どもたちにとっての幸せを追求したい。そうじゃなきゃいけない。だからその芯からブレて自己満足が優先されているときの自分は振り返ったときに気持ち悪い。けれど心をクリアにして、子どもの幸せを追求するためにベストな行動とは、と客観的に見つめ直すと、自分がいることなのか、いなくなることなのか、接し方を変えることなのかがわからない。
「ねえねえ、あのさ」
「んー?」
「……私ってさ、子どもたちとうまくいってると思う?」
ある週末の帰り道、たまらずトンに聞いてみる。
「えっ、なんで? めちゃめちゃ仲良くしてくれてるじゃない」
「そうかなあ」
まあ、そんなふうに聞かれたらそう答えるしかないか。
「あっ、俺があんまり感謝を伝えてないからだね。ごめんね、いっしょに遊んだりしてもらうことがなんか当たり前みたいになっちゃってさ。すっごく感謝してるよ、ほんとにありがとうね」
「うーん、そういうことじゃなくてさ」
「えっ! 怒ってる?」
「あ、ううん、怒ってないけど」
この心のわだかまりを、ちゃんとうまく話せる気はしない。
トンには、私がこうして悩んでいることなんてわからないのだ。今まで、心のどこかでこの問題はトンと共有できる、2人で取り組んでいる問題のような気がしていた。
知らない家族の中に入り込んでいくことは、私という「1」が、どうやって「3」人に受け入れられるかという問題であり、「3」のリーダーを務めるトンは全体を俯瞰していて、子どもたちの本心も把握している人のように見えていた。
でもそんなはずはなかった。トンと私は、ぜんぜん別のものを見ている。
私がいちいち自分の言動や子どもたちの反応を気にして「これでいいのだろうか」と思い悩んでいる現場も、トンには「なんだか仲良くなったようでよかった」レベルの解像度でしか見えていないのだ。
受け取る相手にしかわからないレベルの、微弱な電流の交換のような感情の揺れ。それはいつもいっしょにいる親にも検知することのできないものなのか。もっと言ってしまえば、私とミナトのあいだを流れる電流をマルちゃんは検知することができないし、私とマルちゃんのあいだの電流をミナトは検知することができない。
ならば、私から見たら仲のいい親子に見えている、トンとミナトとマルちゃんにも、私が知ることのできない複雑な感情があるのだろうな。
そう考えていくと、家族の問題って結局は1対1の問題の掛け合わせでしかないんだなあと思う。
普通の家族もそうなのか? そうなのかもしれないな。
そういえば、こんなこともあった。
子どもたちが寝静まってから2人でなんとなくしゃべっているとき、トンが猫の面白かわいいエピソードを話すような口調で話し始めた。
「最近さあ、ミナトのやつ色気づいちゃって」
「なに、どうしたの?」
「朝、一生懸命寝ぐせを直してるんだよ。それで前髪がびしょびしょになっててさ」
「え? ……なんでそのこと笑えるの?」
「え?」
「笑うことじゃないでしょ」
たしかにかわいい笑い話として扱ってもいいような話題だった。猫が顔を洗う動作をかわいいといって笑うような。が、冗談だとしてもミナトをからかうような言い方に怒りを覚えた。
赤ちゃんの頃からずっといっしょにいる親にとっては、子どもが大人びることは笑えることなのか。私は途中参加だから、べつに11歳にもなればまあ寝ぐせくらい直すほうが普通だろうと思って特に面白くはない。
これに限らずだけど、今も昔も、親は子どもに好きな異性がいると知ったり、大人のようなものの言い方をしたりすると、ちょっと馬鹿にするように笑ったりひやかしたりするけど、自分も子どもの頃にやられて心の底から嫌だったし、自分はその愚かさの連鎖に組み込まれたくない。「○○のくせにそんなことしちゃって〜」という嘲笑は身内特有のものなのかもしれないと思う。
それはよくないことだけれど、親は子どもが離れていくことに焦りやさびしさや嫉妬があって、その戸惑いをこんなふうに笑いに包んでなんとか直視しないようにごまかさなければ受け止められないのかもしれない。そして笑っても無駄だと気づいたとき、子どもが自分の手の中にはもういないことを受け入れられるのだろうか。
誰も自覚してないかもしれないくらいの、ささやかな確執を目撃した気がした。
*
○月○日
日曜の昼下がり、4人で近所のスーパーに買い物に行く。ウインナーの試食をやっていて、ミナトとマルちゃんが手を出すと販売員の人から何の疑いもなく、
「どう? おいしい? ね、お母さん、今日はこれとってもお買い得! 2袋で500円です〜」
と言われる。何の疑いもなくもなにも、みんなでカート押してるこの状況で、
「もしかしたら親子じゃないかもしれませんが近くにいる大人の方〜」
って前置きしてくる人がいたらそっちのほうが面倒だし、別にいいのだが、うれしいような恥ずかしいような複雑な気分だ。
ミナトやマルちゃんも聞いていただろうか。どう思ったか気になってしまう。
○月○日
4人でごはんを食べながらバラエティ番組を見ていると、CMに、いかにもな家族団らんの様子が映し出された。住宅メーカーのコマーシャルのようだが、あたたかい料理を作って家族に「おかえり」と言う素敵なおかあさん、食卓を囲むお父さんと子ども、ベッドで眠る子どもを愛しそうに眺め、そっと頭を撫でる両親……。おいおいおい、なんてCMを流してくれてるんだ、と、エロシーンが始まったとき並みにひやっとする。「家族のかたちはそれぞれなんだ! お前たちが無意識に垂れ流している『家族は両親揃ってこそ幸せ』、っていうメッセージが今もこうして子どもたちを傷つけてるんだよ!」という怒りが湧いてきた。
と、ミナトが言った。
「僕このCM好き」
「へっ? どこが?」
「この歌が好き」
そう言うとマルちゃんと2人でサビの部分を歌い始めた。
「へえ……そうなんだ……あ、そう……」
そんなこと気にしてるのは私だけなのか。そうなのかもしれない。私にとっては「父+息子」という組み合わせこそが新鮮だけど、彼らはもう何年もこの設定を生きてきていて、CMで親の揃った家庭の図を見ることなんて、日常茶飯事なのかも。勝手に私が期待してしまっていたのだ。「自分たちには母親がいない」と気に病んでいる子どもたちの姿を。嫌になってしまう。こんなに自由でいたいと自分で言いながら、自分こそが偏見に囚われている。
*
そういえば他にも彼らの指針を感じた場面があった。
4人でコンビニに買い物に行ったとき、またちょっとしたことで2人が喧嘩になり、互いに追いかけ回ったあげくに力いっぱい殴り合って、最終的にまたマルちゃんがわんわん泣いていた。
「これ、家の中だけなのかと思ってた。外でもやるんだね」
半ば呆れて感想を伝えるとミナトがちょっとおどけたように両手を広げて言った。
「そうです。これが僕たち3人の生活でーす」
ミナトのちょっと得意そうな、うれしそうな、顔。あ、こういうことなのか、とそのときすべてが腑に落ちた。
彼らは3人で完結しているのだ。「母」が欠落した家族をやっているわけではない。ミナトはそのことに自信を持っている。
彼らが育つ過程で「うちはお母さんがいないから不幸なんだ」と思って卑屈になるようなパーソナリティーを持つ機会はいつでもあっただろう。そうなってしまう人と、そうならない人の差は何なのだろう。まわりの大人によるものなのかな。特に父親の。
母から父親の悪口ばかり聞かされて育った子どもは父親を憎んで育つ。自分の人生でも、何度か見かけたことがある。それと同じことだ。
多分トンは子どもにも絶対そういうこと言わないだろうな。私ですら、2人の母親の悪口は一回も聞いたことがない。シングルファーザーだから大変だ、という言葉も今までに一度も聞いていない。
こうして、3人と仲良くなればなるほど、最初に思っていた「大変だね」という言葉が自分の感覚にもマッチしなくなっていた。私は大変だね、という言葉を捨てるかわりに、トンの子育てを大げさにほめていくことにした。
「2人ともほんとうにかわいいよね! 意地悪なところとかひねくれたところがまったくないしさ。どっちもそれぞれ違ったよさがあるよね。でも2人ともやさしくていい子だよね。やっぱりトンが育てたからだろうなー」
「へへへ、そうかい? そう言ってもらえるとうれしいなあ」
参考になるというのではないけれど、シングルファーザーの楽しい本を見つけた。漫画家の瀧波ユカリさんが紹介していて知った本で、河相我聞さんの『お父さん日記』。父と息子2人の、ひたすらに楽しくて騒がしくて自由な生活は、友達同士の生活のようでこの家にも似ていた。親は子に何を与えるべきか、なんておどろおどろしく構えた気持ちを忘れさせてくれるような、ただ一生懸命に楽しく日々をいっしょに生きていくことだけのシンプルなありかたを示していた。
はじめてのお出かけ
私の次なる目標は、みんなで少し遠くまで出かけることだった。いっしょに過ごすようになってからけっこう経つというのに、みんなで出かけたところといえば、歩いて行ける近所のスーパーか、コンビニか、ファミレスくらいのものだ。だいたいこの家族はほんとうにほんとうにゲームとテレビばっかりで家から出なさすぎる。よくない。ほんとうは子どもたちだってどこかに出かけたいのではないか?
私が最近読みかじった、有名な育児の専門家の佐々木正美さんも「子どもがゲームをやりすぎる問題については、取り上げることや時間を制限することばかりを考えるのではなく、愛情を与えてないことに注意すべき。親の愛が伝わる他の何かを子どもに湯水のように与えれば問題なし」(意訳)と書いていたのでなるほどと思い、あれこれ考えた。子どもがよろこぶといえば、やっぱりあれだろう、あれじゃないか。
「みんなでさー、ディズニーランドとか行きたいね!」
と主張してみるが、全員返事なし。ジェットコースターとかいろいろあるんだよ、行ったことある? あと、パレードとかもあるし……楽しいよ……きっと……多分……と、あまりのノーレスっぷりに心が折れて主張がもごもごとフェイドアウトしていった。やっぱり男の子だからミッキーとかはあんまり興味ないのかな。じゃああれだ。
「それか、富士急ハイランドとかは? めちゃ怖いジェットコースターとかいっぱいあるんだよ!」
またも全員返事なし。見かねたトンが申し訳なさそうな感じで、
「ミナトは乗り物酔いするんだよなあ。だから遠出は無理かも」
それに乗るかたちでミナトも、
「ないわ〜」とひとこと。
「ないわハウス!」マルちゃんがミナトに続いて言う(ダイワハウスとかけたオリジナルギャグらしい)。
「え、そうなの? 車がだめってこと? 電車なら?」
「電車もむり」
マルちゃんも続く。
「ていうかー、出かけるのとかめんどい! 家がいちばん」
夢は早々に打ち砕かれた。子どもって遠出とか喜ぶものかと勝手に思ってた。新しい体験をしたりしたくないのかね。もしくは友達がどこかに連れて行ってもらったとかいう話を聞いてうらやましくなったりはしないのか。でもトンが出不精だったら、子どもも「それがいいんだ」って思うものなのかもしれないな。
家でいつも暴れまくっているのは、思いっきり遊んでいないストレスによるものなのではないかと勝手に解釈していた。しかし少なくとも意識上では外で思いっきり遊びたいというわけでもないらしい。
とにかくデカイ提案は敬遠される。私は子どもたちが何なら食いつくのかを探りまくった。そしてついにお出かけ案が初めて採用された。行き先は自転車で15分ほど行ったところにある「くら寿司」である。くら寿司の子どもウケがすごいという情報を入手し、もしかしてこれならイケるのではないか? という手応えを感じていた。彼らももともと回転寿司は好きらしいが、くら寿司には行ったことがないらしい。
「くら寿司は、食べ終わったお皿を入れる穴みたいなのがテーブルにあって、5枚入れるとガチャ1回できるんだよー! あと、お刺身だけじゃなくてハンバーグとかコーンのお寿司もあるし、ポテトとかチキンもあるよ」
という誘い文句でついに子どもたちの興味を引くことができたのである。
「自転車で行くの? ならいいか。サーモンあるかな」
「あるある、サーモンめちゃめちゃある」
「俺がみんなの分もガチャやる! ね、いい? いいでしょ?」
「うん、マルちゃんお皿入れる係ね」
くら寿司行きが決まると、さっそく私は次の週末にそなえてアプリで席を予約し、自転車で行きやすい道を確認する。
でも自分で決めておきながら思った。そんなに遠くまで、行けるのだろうか?
はじめて子どもたちと外の世界に出るような気分。日が暮れ始めて、うす青の空に金星が輝いていた。自転車4台の旅。それぞれが漕ぎ出し、バラバラになったり近寄ったりする。私は自分でも不思議なほど、子どもたちが車に轢かれないか心配で、きちんとついて来れるのかが心配で、列のいちばん後ろについて3人の走る姿をハラハラしながら見守った。生まれたての子猫をかごに入れてはじめて外に連れて行くときはこんな気持ちだろうか。
彼らは乗り慣れた様子ですいすいと自転車を漕いだ。そうか、そりゃそうだよね、もう5年生と2年生なんだもんな。なんでそんなふうに思っていたんだろう。そう頭では理解していても不安で、とにかく彼らが事故にあったり怪我をしたりしないように見守らなければ、というような気持ちに囚われた。
ちがう。生まれたてなのは彼らではなくて、私なのだ。だからこんなに不安なんだ。でも走れている。どんどん空が暗くなる中でいっしょに自転車で走っていると、彼らとの距離が少し近くなったような気がする。歩道橋を渡り、高架をくぐり抜け、いくつもの信号を渡りながら。
くら寿司の予約時間よりかなり早く着いたので、同じショッピングモールの中にある100円ショップに行くと、突然トンがバラエティー番組のような企画を通達する。
「ひとりずつ、これは面白い! と思うものを5個買って、あとでくら寿司で発表大会しよう。お金渡すから、他の人に何を買ったかばれないように各自で買って集合な!」
かけ声とともに、みんなで広い店内の方々に散って、ウケそうなものを物色する。パーティーグッズコーナーはすでに子どもたちが先回りしていて、追い出すようなジェスチャーをするので仕方ない、ペット用品やお菓子コーナーでいいものがないかを探す。通路などで出くわすとお互いカゴを見られないように大げさに隠す。買った商品をそれぞれビニール袋に入れて店の前で再集合し、くら寿司に向かった。
せまいテーブル席で、寿司も取らずにみんなが買ったものを1個ずつ取り出す。そのたびにトンと私の2人で場を盛り上げる。おもちゃのピストル、うんこの形のお菓子、やたらと長いガム、ゾンビのお面。ひとりずつお面をつけて記念撮影をして、ひと盛り上がりし終わったところでやっとお寿司を注文し始める。ミナトは狂ったようにサーモンばかりをオーダーし、マルちゃんはあいかわらずしゃべったりふざけたりするばかりで最初の1皿さえもなかなか食べないで、人の食べ終わった皿を回収することに燃えていて、大騒ぎだった。でもファミリー向けのお店の中は満員でかなりにぎやかだったから、騒いでも目立たず、誰からも怒られなさそうで安心した。
騒いだあとの帰り道は、海かプールにでも行ったときのように、心地よい疲労と、抜け切らない楽しさの余韻が入りまじって、張り詰めていた気持ちが自然とやわらいでいた。
「パパー。パパー。なんかだじゃれ言ってよ」
「突然すぎるだろ! えーと、じゃあねえ……『猫がねころんだ』! はい、次マルちゃん」
「えー、俺はねー、俺は……んー……『うんこ食べたいな!』」
「全然だじゃれじゃないじゃん、だめ! 不合格!」
「あ、僕ある」
「じゃあ、はい、ミナト」
「『ふとんがふっとんだ』」
「いいね!」
「はい次、花田さん」
「えっ、やばい、何もない……うーんうーん……あっ! 行きます。『父さんの会社が倒産』」
「とうさん? つぶれたってこと? うーん、どうする?」
「うーん、まあアリ」
「よかったー」
「じゃ、次ナシなの言った人の負けね。はい、マルちゃん」
「いいのあった! えーとね、『カエルが帰る』!」
「いいじゃーん」
「いいねいいね」
「あ、僕すごいのある! あーこれ言ったら負けちゃうかもなー負けちゃうなー」
「え、なになに」
「どういうこと?」
「負けちゃうかも……。じゃあ言うね。『はい、僕の敗北です』」
「ん?」
「お!?」
「なに今の。すごいじゃん! もうこれミナトの優勝じゃない?」
「今の前フリがよかったね。じゃあ、ミナトの優勝で!」
「よっしゃー!」
車がほとんど通らない、無駄に広い通りを、4人で自由に広がりながら漕いでいく。もう何も怖くなかった。月が頭上までのぼっていた。
試し読み プロローグはこちら
試し読み 第1章はこちら
試し読み 第2章はこちら
予約受付中!!! 花田菜々子
花田菜々子
シングルファーザーの年下彼氏の 子ども2人と格闘しまくって考えた 「家族とは何なのか問題」のこと」
1400円(税別)
46判/224ページ
2020年3月下旬発売予定