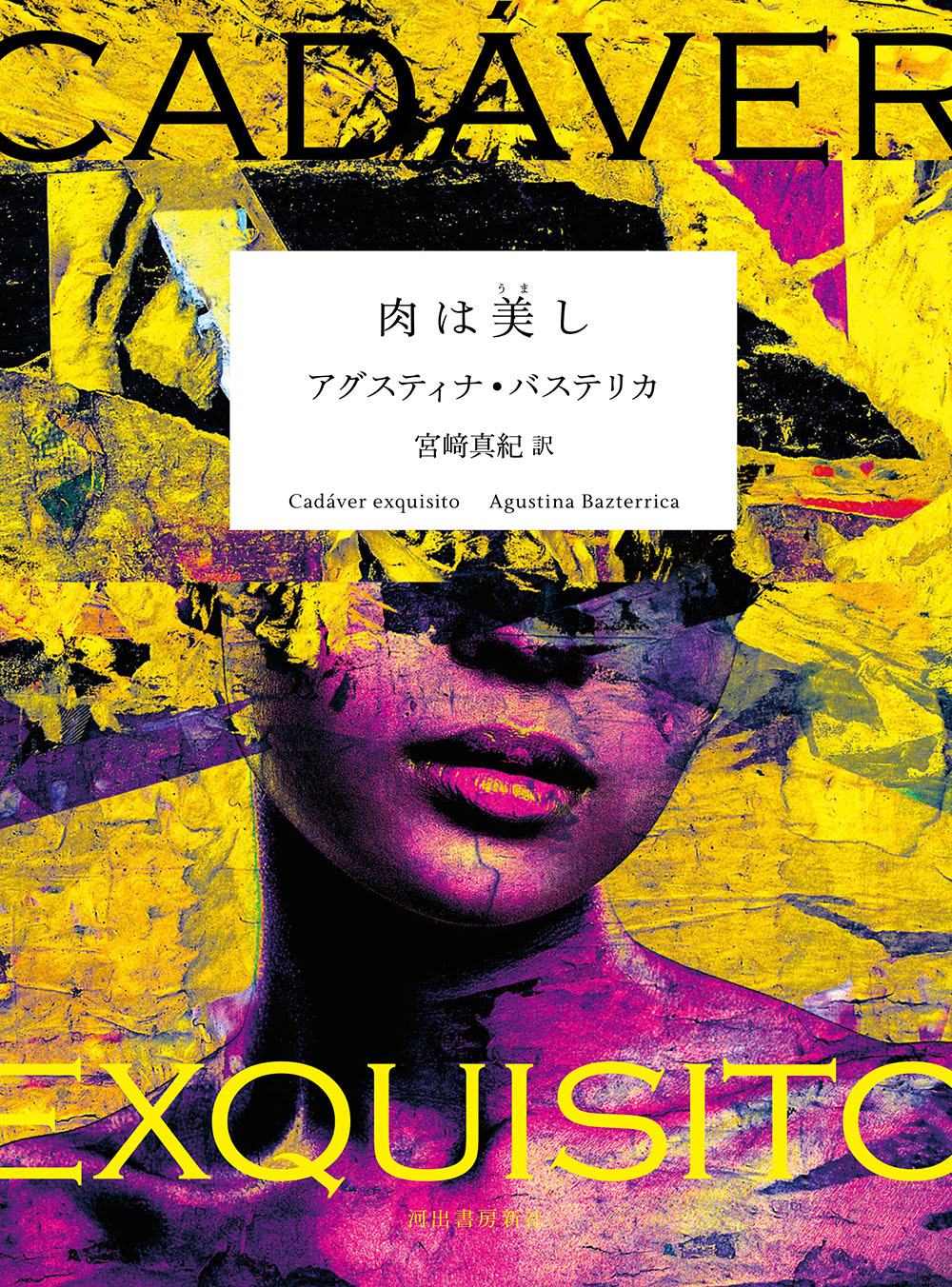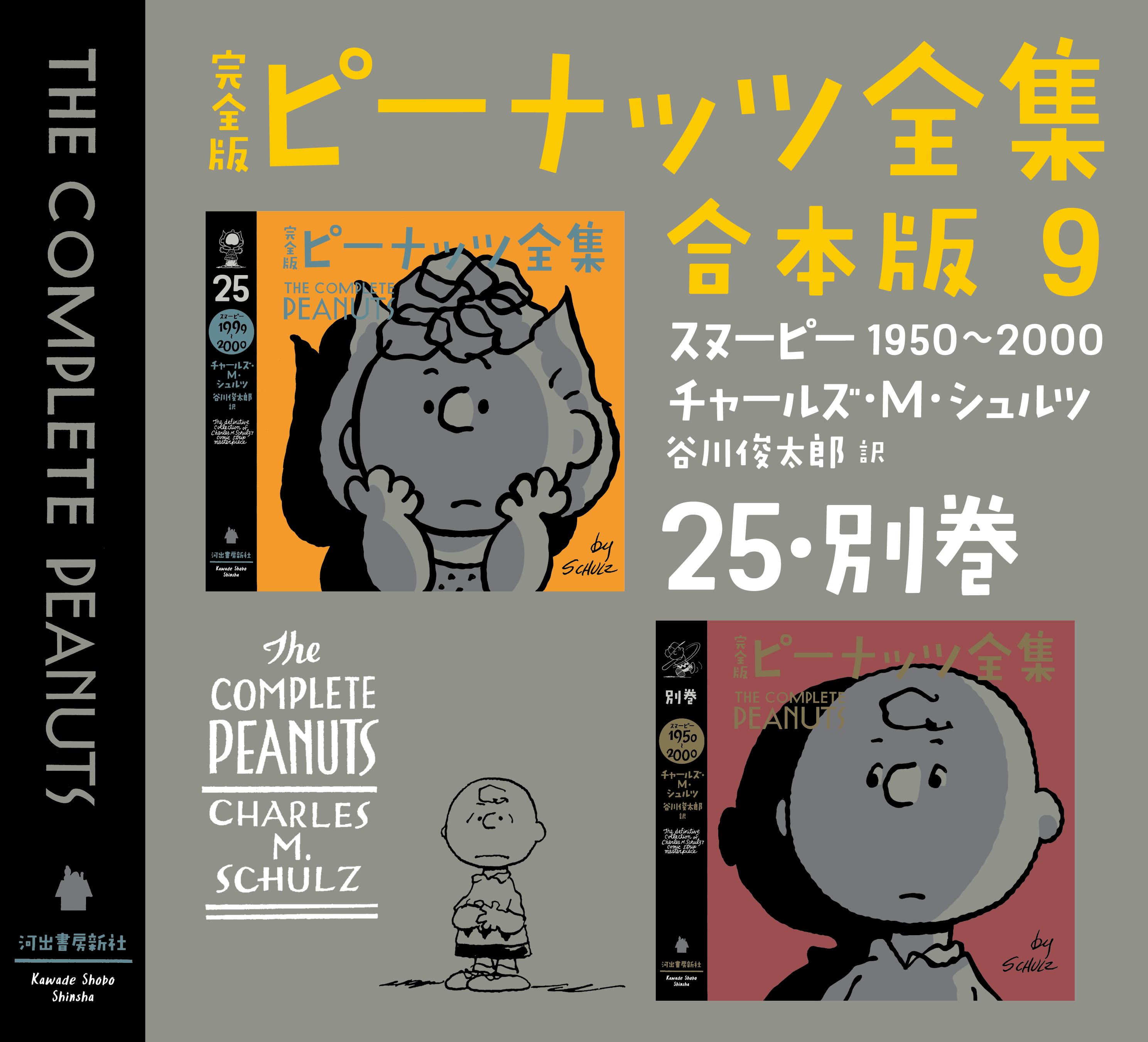単行本 - 外国文学
『青い脂』のモンスター、ソローキン「氷三部作」完結記念、『ブロの道』試し読み公開
ウラジーミル・ソローキン
2016.08.29

『ブロの道』
ウラジーミル・ソローキン 著
松下 隆志 訳
ツングース隕石探検隊に参加した青年が巨大な氷を発見し、真の名「ブロ」と「原初の光」による創造の秘密を知る。20世紀ロシアの戦争と革命を生きた最初の覚醒者をめぐる始まりの物語。
アヴァンギャルドから物語の最前衛へ。
ソローキンにしか書けない超絶スペクタクル小説。
憧れる。
——中原昌也
そこの肉機械のあなた、ソローキンさんが世界の成り立ちをわかりやすく書いてくれましたよ、肉機械用に。
——藤野可織
—————-【試し読み公開】—————-
氷
目を開けた。
暗く、土の臭いがつんと鼻を突いた。身じろぎし、暗闇で片手を伸ばした。土と根に触れた。冷たい土がぱらぱらと降りかかる。私はすぐに、自分が誰で、どこにいるかを思い出した。そして、自分の穴から出ようとした。私の隠れ処となった、地上に垂れ下がる、年老いたカラマツの根でできた〈屋根〉の下から這いだし、ぴたりと動きを止めた。辺りは一面、明るい月光に浸されていた。頭を上げる。濃紺の空に、鏤められた星に囲まれ、巨大な満月が浮かんでいた。目映さのあまり、私は目を逸らして辺りを見回した。地平の彼方までこの信じがたい光が降り注いでいる。幻想的な光景が目の前にあった。照らされたいくつもの丘は、目に見えない大海原の凍りついた波を思わせた。流れ流れては集い、ぶつかりながら、波たちは遠くへ、仄明るい東の空へ去っていく。死んだ林は完全な静寂のうちにあった。物音一つ、葉擦れ一つしない。そして、その真っ只中に私は立っている。一人で。
だが、恐怖はない。逆に、古木の根の下での深い眠りが、力と落ち着きを与えてくれた。絶えず私を揺さぶっていた興奮は体を去った━━まるで、地中に流れ去ったかのように。私は月に向かって両手を上げ、愉悦とともに伸びをした。
そして、唸りだした。
私は自由だ!
隣には誰もいない。誰も私を笑わない、命令しない、頼まない、催促しない、ばかげた助言をしない、マルクス主義や天文学を論じたりしない。この一ヵ月間ずっと、蚊のように私に付きまとっていた憎むべき言葉の群れは散り、人々と一緒に消え去った。世界の完全な静寂は感動的だった。私の前で、地上の世界が大いなる平安の中で停止している。そして私は生まれて初めて、この世界の被造性を感じた。この世界はひとりでに現れたのではない。それは盲目的な諸力の偶然の結合の結果ではない。世界は創造されたのだ。意志の力によって。ある瞬間に。
この発見は私を揺さぶった。私はひんやりとする夜気を吸い込んだ。そして、吐き出すのが怖くなって、息を止めた。哲学や宗教の本、存在や時間、形而上学についての議論は、私がいる世界への理解をまったく何一つ与えてはくれなかった。月光に浸された死のタイガの真っ只中でのこの瞬間が、私に偉大な秘密を開示したのだ。
私は息を吐き出した。
そして、足を踏み出した。
私の心臓が今やお馴染みの躍り方をした。そして、私は巨大で懐かしいものを思い出した。唖の恍惚の中で震わせ、夜も寝かせず、倦まず歩かせ、歯を食いしばって沈黙させたものを。それはすぐ隣にある。再び、それを心臓で感じた。しかし、もはや穏やかに、涙も戦慄も抜きに。巨大で懐かしいものが私を呼んでいる。そして私は、その呼び声の方へ歩きだした。
黒ずんだ幹の間を歩いた。月が後を追いかけてきて、進むべき道を細部まで照らした。私は足元にある石の一つ一つを、折れた枝の一本一本を目にした。月が、焼け焦げた幹の上でたゆたっていた。幹たちは無煙炭のようにきらきら輝いている。繁茂した苔がブーツの下でぐにゃりと撓む。歩くのは容易だった。背後にはもはや何もなかった。缶詰も、脂身も、乾パンもない。人間と結びつくものは何もない。しかし、そのことは怖くない━━飢えはまったく覚えなかった。この一ヵ月の間に私が感じた内側の恍惚のすべてが、今やある一つの平静で堅固な願望に変わった。巨大で懐かしいものの元へ行きたい、そしてそれを見つけたい、という願望に。
私は歩いた。
足は生命のない野生の風景を軽々と克服していった。私は歩いた━━一時間、二時間、三時間。いくつもの丘がゆっくりとそばを流れていった。やっと丘は平らになり、脇へ退いた。そして、月光が筋のような水の中できらりと光った。
沼だ!
私はそこに近づいた。
気化した薄い霧が以前のようにその上に掛かっていた。心臓が強く打ちだした。抗しがたい力でそこへ引き寄せられた。懐かしいものがそこにある。そして私は、一歩前へ踏み出した。すっぽり土を覆い隠している足元の苔が撓んだ。苔むした沼地が大きくなり、間もなく、粘着性のある泥が足元でべちゃべちゃ音を立てはじめた。一歩ごとに心臓の鼓動が強くなった。しかし、これは動揺や興奮で起きる動悸ではなかった。心臓が打つ回数は減ったが、よりいっそう強く、重々しくなった━━一回一回の鼓動が胸の中で反響し、その波が体中に伝わった。あたかも心臓が体の生から独立し、自らの生を生きはじめたかのようだった。その均等で重々しい鼓動は私を甘く揺さぶった。体は、この鼓動のリズムに合わせて共鳴した。ブーツはどんどん深く沈み、歩行が困難になった。沼の泥が上がってきた。間もなく腰まで浸かった。冷たい水がどっとブーツに流れ込み、脚を包み込んだ。これは永久凍土の冷たさだった。月は明るく、素知らぬ顔で私を照らしていた。心臓の轟く鼓動は恐怖が入り込む隙を与えなかった。ひどく先へ進みたかった。そして、全力で突進した。氷のように冷たい沼に足を取られたが、私の方が強かった。盛り上がった場所を両手でしっかりつかみ、先へ進む。一歩、二歩。そして、困難きわまりない十歩。
二十歩。
百歩。
でこぼこ道が終わった。前方には平らで、アオウキクサにうっすら覆われた沼沢地があった。私は百一歩目を踏み出した。そして胸まで浸かった。しかし、心臓の鼓動はもう完全に耳を聾するばかりで、一回脈動するごとに、私を前に突き出した。浮草から突き出している、折れた古木の腐った幹にすがりついた。そして、前方が深くなっており、泥濘んでいることがわかった。だが、この泥濘の上には水の層があった。この水なら泳いでいける。泳いで進むためには、着ているものを全部脱ぐ必要がある。幹につかまり、激しい動きで泥濘から足を引き抜き、体を伸ばし、木の残骸に腰かけた。濡れて体に貼りついた衣服を脱いだ。水が溜まったブーツをやっとのことで脱いだ。裸になり、幹から離れ、蛙のようにぴょんと前に飛び込み、手で水を掻き、足で蹴った。信じられないことに、私はまるで湖を泳ぐようにして沼を泳いでいた。泥濘の上、浮草の下にある水は澄み、冷たかった。止まらずに前へ泳ぎつづけるだけでよかった。もし止まれば死あるのみで、泥濘に吸い込まれる。腐った藻が腹を擽り、曲がった木が引っ掛かる。だが、恐怖は背後に、人間の世界に置いてきた。私は少し泳ぎ、不意に悟った。巨大で懐かしいものはもうすぐそこにある。あともう少し━━それで手を触れることができる。
心臓が激しく鼓動しはじめ、目の中にバラ色がかったオレンジ色の虹が輝きだした。体が急に温かくなった。それから、熱くなった。
恍惚が私を捉えた。
人間の言葉を忘れた固く結んだ口から、嗚咽が逬った。私は理解した、巨大で懐かしいものに触れることができなければ、自ら溺れ死ぬだろう。それがなくては生きる意味などない。それ以外、私には何もない。人生で一度も、これほど強く何かを願ったことはなかった。
掻き分けられる水が、月明かりの中できらきらと輝いた。緑色の浮草が水面をたゆたっていた。
神々しい静寂が辺りにあった。
両手で一掻きすると、体が前に滑った。
さらにもう一掻き。
もう一掻き。
もう一掻き!
もう一掻き‼
もう一掻き!!!
両手が氷に触れた。
そして、自分がここにやって来た理由を理解した。
そして、幸福のあまりわっと泣きだした。
巨大で懐かしいものを見つけた! 指が滑らかな表面に触れる。心臓は耳を聾するように鼓動している。今にも気を失いそうだ。頭が一瞬にして浄められ、頭の中で神々しい空虚が鳴りだした。熱に浮かされた指は、ずっと水面下の氷を触りつづけていた。大声で泣きながら、私は咽びだした。氷の縁は上に向かって滑らかに延びている。私は死に物狂いで水を突いた。そして、トカゲのように氷に這い上がった。氷を覆う水はほんのわずかだった。身震いし、号泣しながら、氷のレンズの上を先へ先へと這う。辺りは、遠く離れた丘まで、浮草に覆われた平らな沼沢地が開けていた。巨大な氷塊は沼に埋没し、水面下で眠っていた。この懐かしい塊は、二十年もの間静かに横たわり、私を待っていたのだ。私がこの氷を見つけるのに二十年も必要だった! 号泣で体が撓む。体が熱で火照っている。心臓の鼓動に揺さぶられる。息切れしながら、沼の湿った空気を呑み込んだ。前方で緑色の浮草が僅かに脇へ退いていた。月明かりの中で氷がきらりと輝いた! 純粋な氷の一部だ! 起き上がり、その方へ駆けていく、水を撥ね散らし、眠たげな千歳の浮草を払いながら。氷! 氷は白く、青く輝いていた! なんたる純粋さ! なんたる力強さ! なんたる懐かしさ!
永久に私の、私のものだ!
たどり着き、足を滑らせた。
そして転んだ。輝く氷に力任せに胸を打ちつけた。
意識が遠のいた。一瞬。
その後、あたかも私の心臓が氷にぶつかった衝撃で鳴りだしたようだった。そして私は、たちまち氷の塊全部を心で感じた。それは巨大だった。そして全体が振動し、私の心臓と共鳴した。私一人だけのために。この二十年間ずっと胸腔で眠っていた心臓が目覚めたのだ。鼓動が激しくなったのではなく、どくんと突かれたような感じで、最初は痛かったが、後から気持ちよくなってきた。そして、おののきながら語りだした。
「ブロ・ブロ・ブロ……。ブロ・ブロ・ブロ……。ブロ・ブロ・ブロ……」
私は理解した。これが私の本当の名だ。我が名はブロ。私はそれを全身全霊で理解した。私の両腕が氷を抱いた。
「ブロ! ブロ! ブロ!」心臓がおののいていた。
そして、氷の塊は私の心臓に応えた。その神々しい振動が私の心臓に流れ込んできた。氷は振動していた。それは地球上のどの生物よりも歳を取っていた。その中で永遠調和の音楽が歌っていた。それはあらゆる比較を絶する。万物の始原の始原の音を奏でているのだ。胸を氷に押しつけ、永遠調和の音楽を聴きながら、私はぴたりと動きを止めた。この瞬間、地上の世界はすべて色を失い、透明になった。そして、消えた。私は氷と二人きりで宇宙に浮かんでいた。星々と沈黙の間で。
そして、私の目覚めた心臓が永遠調和の音楽に耳を傾けはじめた。
——————————-
〈氷三部作〉完結記念
『氷』試し読み 公開
『氷』訳者あとがき 公開
『ブロの道』訳者あとがき 公開