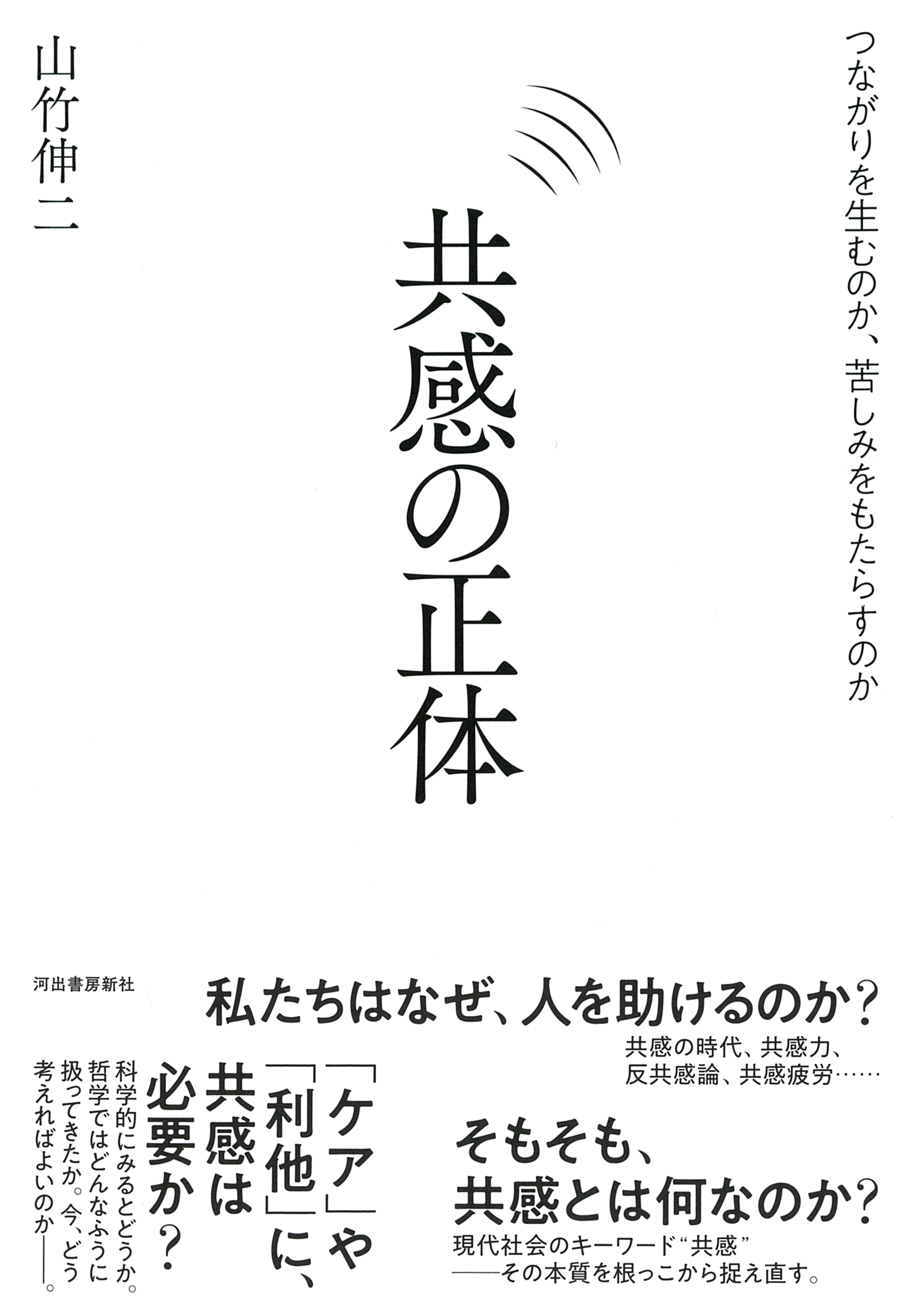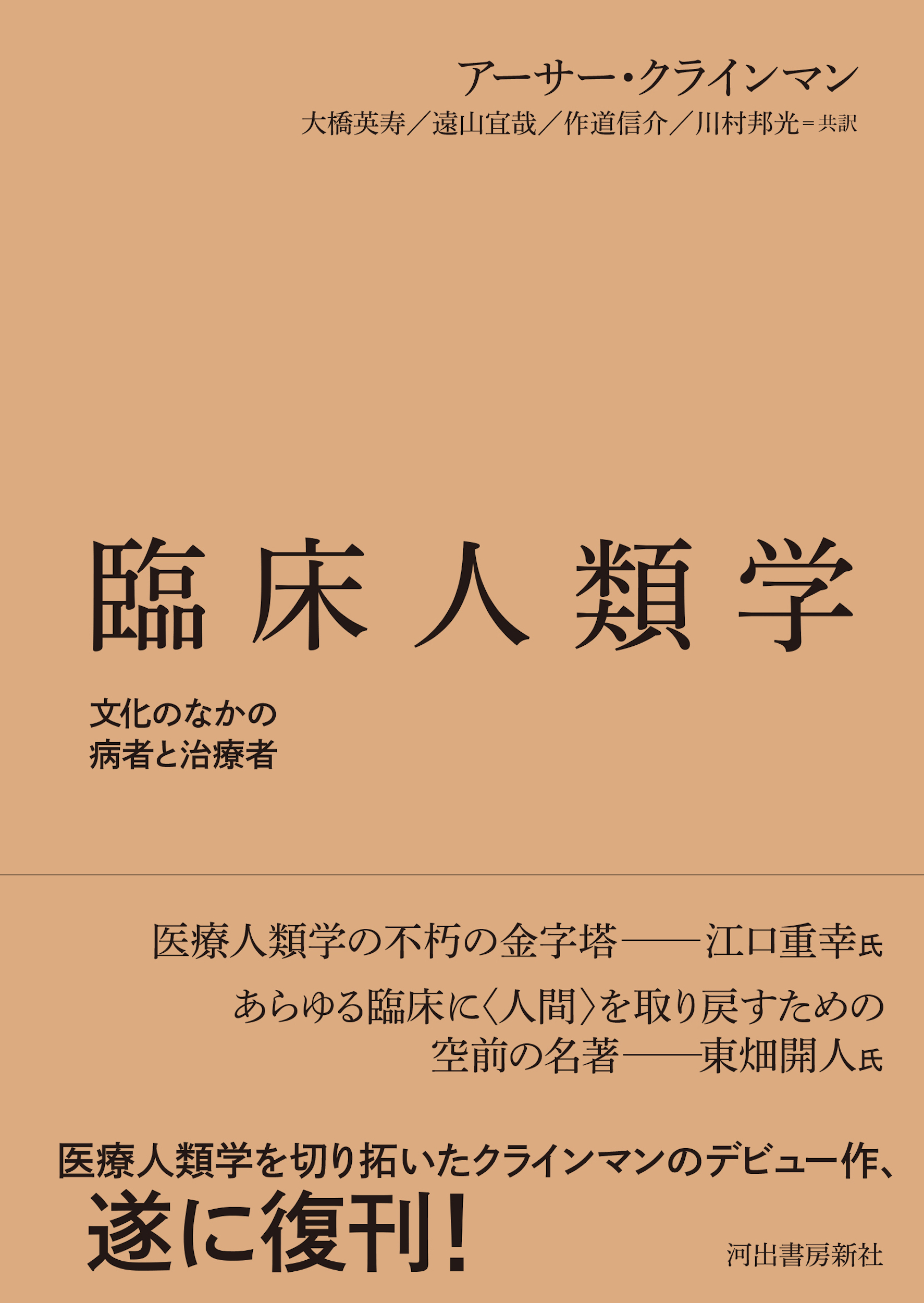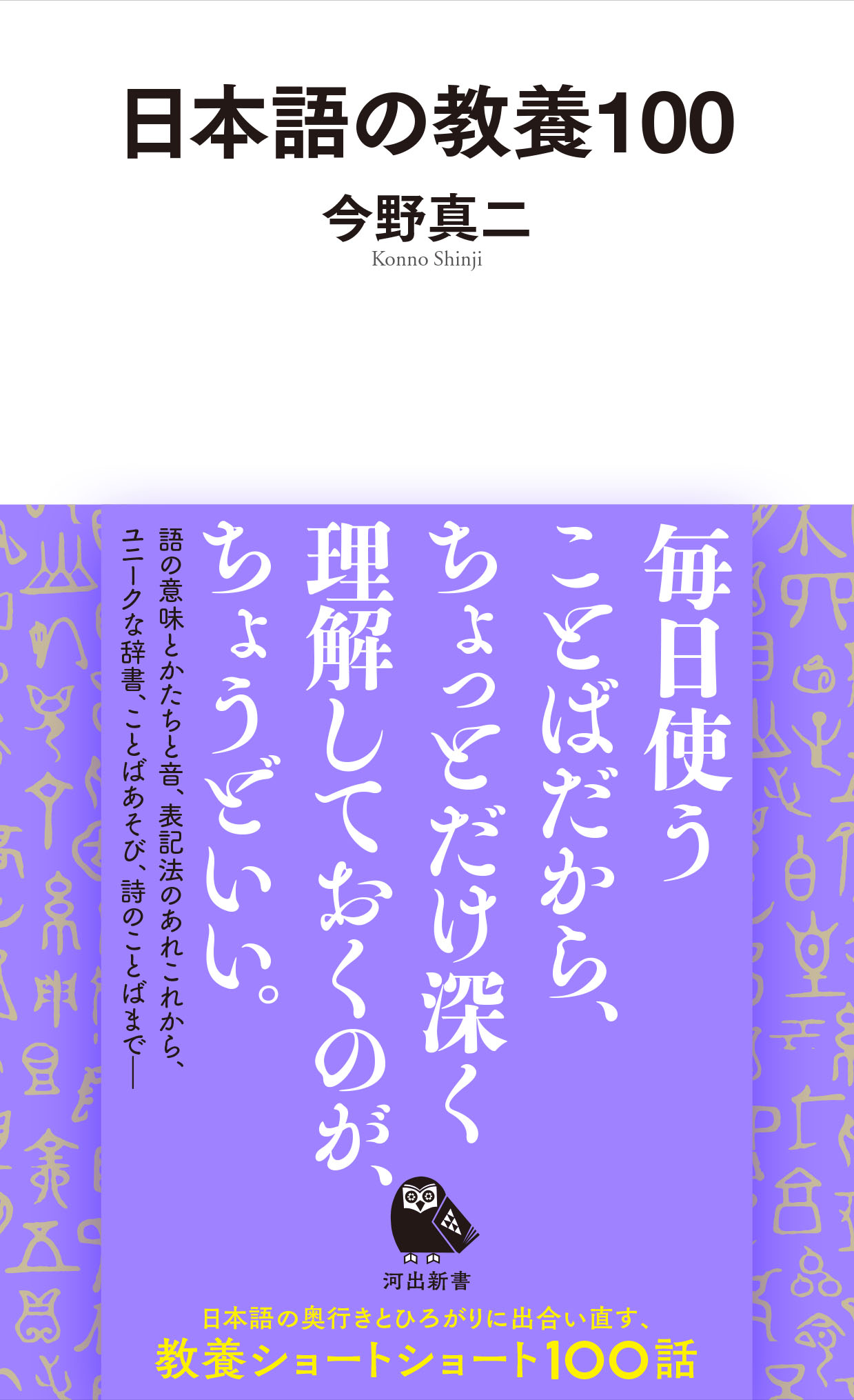
単行本 - 人文書
今野真二『日本語の教養100』(河出新書)刊行記念 往復書簡 「知識の沼――ことばで巨人の肩にのる」第10回(最終回) 今野真二→山本貴光
今野真二
2022.01.05
10年以上にわたって多彩な視点から日本語をめぐる著作を発表しつづけてきた今野真二さん。その日本語学のエッセンスを凝縮した一冊とも言える『日本語の教養100』が刊行されました。これを機に、今野日本語学の「年季の入った読者」と自任する山本貴光さんとの往復書簡が実現。日本語についてのみならず、世界をとらえるための知識とことば全般に話題が広がりそうな、ディープかつスリリングな対話をご堪能ください。
第1回はこちら。
第2回はこちら。
第3回はこちら。
第4回はこちら。
第5回はこちら。
第6回はこちら。
第7回はこちら。
第8回はこちら。
第9回はこちら。
* * * * *
山本貴光さま
早いもので、もう最終回になってしまいました。こういうかたちでやりとりを公開することは初めてだったので、最初は不安がなかったわけではないのですが、すぐに楽しいものとなりました。全体のまとめみたいなことは「往復書簡」にはふさわしくないように思いますので、これまでと同じような調子で書きたいと思います。
これまで、「対話」ということがしばしば話題になってきましたが、今回はその「タイワ(対話)」という語そのものについて少し書いてみたいと思います。そのようなことを考えたことには理由があります。
最近、必要があって、賀茂真淵と本居宣長について調べていました。真淵と宣長といえば、二人の出会いを描いた「松坂の一夜」が有名です。「松坂の一夜」は『尋常小学国語読本』巻11に収められてひろく知られるようになりました。教科書のもととなったと思われる文章は佐佐木信綱の『賀茂真淵と本居宣長』(広文堂書店、1917)、『増訂賀茂真淵と本居宣長』(弘文社、1934)に載せられています。できすぎた話のように感じますが、まったくのフィクションではないのです。
宣長は幾つかの日記を残していますが、その中で単に「日記」と呼ばれている日記の宝暦13(1763)年5月25日の条に、「岡部衛士当所新上屋一宿、始対面」と記されています。これが「松坂の一夜」のことと思われ、真淵と宣長とは松坂の「新上屋」の一室で対面したことが事実であることが確認できます。宣長と真淵とが同じ空間にいて、実際にことばをかわしたのは、おそらくこの、5月25日の一度だけだろうと考えられています。こういう師弟関係も江戸時代にはあったわけです。
宣長は真淵と実際にことばを交わしたことを「対面」という語で記しています。この「対面」について、『本居宣長全集』第4巻(筑摩書房、1969)の「解題」において大野晋(1919-2008)は「単に面会することではな」く、「時や場所を定め、場合によっては余人を遠ざけて談合し、あるいは議論することである」(22頁)と述べています。また「「対面」は正式に相対して語ることではあるが、そこに上下の関係は固定していない。上から下に対することも、下から上に対することも、ともに「対面」である。宣長が堀景山の宅に始めて行ったとき、同時に景山の「子息禎治殿ニモ始テ対面」と宣長は書いている。しかし、景山に対しては、「始テ謁ス、酒吸物出ル」と書いている。宣長は真淵に対し、面会を申入れ、新上屋で正式に相対して学問について語った。それは「始対面」したのであって、結果において、宣長は「謁ス」と書くことはできなかったものと私は思う。宣長は、その年十二月二十八日、真淵から入門の許可を得た。その日の日記でも、五月二十五日を回想して「始対面」と書いている」と述べています。
「謁」は「謁見」「拝謁」の「謁」で、〈まみえる〉という意味があります。「マミエル」は単に〈顔を合わせる・対面する〉という意味で使われることもありますが、基本的には「アウ(会)」という意味をもつ謙譲語なので、〈お目にかかる・お会いする〉という意味です。宣長は漢学者堀景山に対して、敬意をもって「謁ス」と記したけれども、そこに「対面」という語を使わなかったところに大野晋は注目したわけです。しかし、さらにいえば、堀景山の子息、禎治に対しては「対面」という語を使っており、それは「上下の関係は固定していない」ことを示しているけれども、なぜ禎治には「対面」という語を使ったかということについては大野晋は述べていません。ここはさらに「情報」がなければ判断できないところになりますので、そちらにはふみこまないことにします。
大野晋は述べていませんが、「タイメン(対面)」の「対」の〈むかう〉という意味は物理的に向き合うという意味よりも、もう少し改まった意味があったのではないかと想像します。「対」についても少し考えてみたいと思います。
「対」を含む語として「タイワ(対話)」があります。『広辞苑』第7版は「たいわ」を「向かい合って話すこと。相対して話すこと。二人の人がことばを交わすこと。会話。対談」と説明しています。語釈末尾の「会話」「対談」は類義語としてあげられているのだと思います。「会話」と「対談」であれば、「対談」は「対話」にちかいけれども「会話」はそうでもないのではないかと思うのです。
どんどん話がひろがっていくような感じになりますが、もう一つ「会談」を加えてみましょう。西郷隆盛と勝海舟とが会談した。これは自然な文にみえます。『広辞苑』は「かいだん」を「(責任のある人が公に)面会して話し合うこと」と説明しています。「責任のある」は何か公的なことについて、あるいは少なくとも私的ではないことについて、ということでしょうから、「公に」と重なってきます。つまり「カイダン(会談)」という語を使う場合には何らかの「公性」がかかわっているといえそうです。
「タイダン(対談)」にはそうした「公性」はなさそうですが、私的であるにしても「あらたまった感じ」は強いのではないでしょうか。現代日本語でも、「対談の企画」といえば、それなりの人がそれなりの場で、ということを想像するでしょう。現代日本語の例を考えてみましょう。勝手に例文を考えました。「うちの子と隣の道夫君との対談を録音した」はおかしく感じますが、「うちの子と隣の道夫君との会話を録音した」はおかしくないように思います。では「うちの子と隣の道夫君との対話を録音した」はどうでしょうか。少しおかしく感じないでしょうか。現代日本語の「タイワ(対話)」には「タイダン(対談)」ほどの「あらたまった感じ」はない。しかし、「カイワ(会話)」よりはそれがある、ということではないでしょうか。「タイワ(対話)」「カイワ(会話)」「タイダン(対談)」は類義語といってよいと思いますが、少しずつ(副次的な)語義が違うわけです。
もう少し話を続けます。アメリカ人の宣教師で医師でもあったヘボンが編纂し、慶応3(1867)年に出版された『和英語林集成』という和英辞書があります。この辞書で「タイワ」を調べると、「Talking face to face, conversation, Syn.TAIDAN」と記されています。「face to face」は対面して、ということですね。「Syn」(類義語)として「タイダン(対談)」があげられています。この「face to face」すなわち対面、ということがそれなりの「あらたまった」ものであったと想像するのです。「メンゴ(面語)」という漢語もありますが、『日本国語大辞典』は「対面して語ること。会って話すこと。面談」と説明しています。「三者面談」というのがありますね。
さて、そうなってくると、「対話による学び」といった時に、少し心構えが必要になるかもしれません。つまり、「対話」は「雑談」とは少し違うということです。大枠としていえば、「雑談」の中にも気づきはあり、学びもあると思います。ですから、「雑談」「会話」大歓迎です。楽しい会話から学ぶということはいいことだと考えます。ですので、「雑談」「会話」はだめだ、というのではまったくありません。
その一方で、「対話」の「あらたまった感じ」はそれはそれで大事にしたいとも思います。誰かと「対話」をするために準備をする、いろいろと調べてみる、そうしたことによって、話題が拡散しないようにする。「対話」の相手に論文や著書があるのだったら、少し目を通す。こうしたことは「対話」の相手を尊重する、相手に気配りをする、ということで、これは「対話」を円滑に展開させ、「対話」を充実させるためには有効だろうと思います。
先日、今野が勤務先の大学で担当している「知的探求の方法」という初年次向けの授業で、「大学の授業における対面と非対面」というテーマでグループワークを行ないました。実際には、こういう観点についての検討は必ずして、グループでの結論はこういう枠組みの中でしてください、ということを提示して、単に好き嫌いの話にならないようにしました。
その中で、教室でのグループワークと遠隔会議システムを使ってのグループワークは違うのではないかという話がでてきました。学生は教室で対面しているほうがいい、と感じているわけですが、今野が「なぜそれがいいのか」と、さらにふみこんだ問いを出すとその問いには答えにくそうでした。それは、ヒトという生物は、同じ種であるヒトの表情から、言語では説明できないような多くの情報をよみとって、その情報を使いながら、コミュニケーションをはかっているからだろうか、と思いました。
こうしたことについては、すでに一定の結果が出ているのだろうと思います。「微表情(microexpression)」をテーマにした海外ドラマを見たのはずいぶん前のことです。ヒトは言語化できないようなことも認識しながら、生きていると考えると、言語には限界があるということになります。それはそうだろうと思います。しかし、言語にかわるものがない以上、その言語をせいぜい劣化させないようにすることも大事だと思います。
*
山本さんが第9回で学びの楽しさということと「人間につきものの感情の側面」について述べておられます。共に学ぶ「共学」や、「対話によって学ぶ」という場合、そこに自分以外の人間がかかわっています。かかわっている人全員が楽しいのが理想であることはいうまでもありません。楽しいことによって積極的な気持ちがうまれるでしょうし、それが動きのエネルギーになるはずです。
「情動」という語があります。『広辞苑』は「(emotion)怒り・恐れ・喜び・悲しみなどのように、比較的急速にひき起こされた一時的で急激な感情の動き。身体的・生理的、また行動上の変化を伴う」と説明しています。「怒り・恐れ・喜び・悲しみ」は日々の生活の中で、大なり小なり感じるものですが、そうした「情動」がヒトを動かすことがあるということです。感情があまり前面にでない場合は「精神の自由な動き」といってもいいかもしれません。
「楽しく学ぶ」ということについても山本さんがふれてくださいましたが、井上一夫『渡された言葉 わたしの編集手帖から』(本の泉社、2021)を読んでいたら、井波律子さんが『中国文学の愉しき世界』(岩波書店、2002)の「あとがき」で、「いつのころからか、わたしは、勉強は楽しんでやるものだ、自分がおもしろくないことを無理にやっても意味がないと思うようになり、以来、怖めず臆せず、おもしろくて愉しい対象を求めて、古代から近世・近代にいたるまで、中国文学の世界を探求・探検するようになった」と述べていることが紹介されていました。ただし井上一夫氏は「だが、こう言い切る背景に鍛えられた日々があったことを忘れてはなるまい」(135頁)と述べています。井波律子さんは吉川幸次郎の指導を受けているわけです。この「鍛えられた日々」を「学び」にどう位置付ければいいか、ということも「共学」を考えるにあたっての一つの観点になりそうな気がします。
山本さんはご存じだと思いますが、井上一夫氏は、1973年に岩波書店に入社して、日本思想体系編集部、日本近代思想体系編集部、新書編集部をへて、1999年には営業部に異動し、2003年から同社取締役となった人物です。『渡された言葉』の「まえがき」には「わたしは出版社=岩波書店に在職すること四〇年、幸いにして多くの魅力的な方々と接する機会を得ました。そして、本づくりをともにするなかで、数多くの印象的な言葉を聞きます。わたしはこれを咀嚼し、反芻、敷衍することで支えられ、編集者としての幅を広げることができました。本書でとりあげるのはその言葉の数々をめぐるエピソードです。いま「咀嚼」といい、「反芻・敷衍」といいました。これから語るのは、わたしの身体をくぐった「記憶」であって、単なる「記録」ではありません」(3頁)とあります。
「渡された言葉」を自身の中で「反芻」するうちに血肉化していくということも「共学」の一つのかたちかもしれません。そしてさらに「本書に掲げる言葉の数々は企画をめぐるやりとりだったり、インタビューのときだったり、雑談の機会だったり、場面はさまざまですけれど、「教えを垂れる」というかしこまった雰囲気だったことは一度もありません。さりげない示唆やふとしたつぶやきを含め、つねに「どう受けとるかは君しだい」というニュアンスが感じられました」(4頁)とあります。
これは、ことばを受けとる側であった井上一夫氏が感じていたことです。つまり、渡す側は、ごくごく自然であったということですよね。しかしまた、「どう受けとるかは君しだい」は大袈裟にいえば、受け手の力量が問われていることになります。「力量」はおおげさすぎるとしても、受けとる側にも「準備」とか「こころがまえ」とか「覚悟」とか、そういうものは必要ではないかと思ったりもします。渡し手、受け手が(ほどほどでいいとしても)相手に気配りをする、その気配りによって「楽しい空間(親密な空間)」をつくり、それを持続させる、そういう気持ちは大事になってくるように感じます。
言語には「話し手・書き手」がいて、「聞き手・読み手」がいるということを毎年学生に伝えています。考えてみればあたりまえのことで、わざわざ言わなくてもいいようなものですが、一般的にいえば、話したり書いたりしかしない人もいなければ、聞くだけ、読むだけの人もいないことになります。つまり「双方向的」だということです。
人間がそのように認知しているからか、そこはまた考える必要があるのかもしれませんが、人間をめぐることがらには「双方向的」なことがらが少なくないように感じます。動きではなくて、状態でいえば、表裏一体でしょうか。吉川幸次郎は、本居宣長が「世界は善と幸福とのみでは満たず、悪と不幸とが、必ず並存する。これは神の意志としてそうなのであって、神には善神もあり、悪神もある」(日本の思想15『本居宣長集』筑摩書房、1969年、4頁)ことを述べていることを高く評価しています。双方向や表裏に目を配る、これは大事なことだと考えます。
2021年10月8日に亡くなった白土三平に『サスケ』という作品があります。今調べてみると、1968年にはテレビアニメ化されていたとのことなので、今野はちょうど10歳でこのテレビアニメを見ていたことになります。このアニメの最初に流れるナレーションの冒頭が「光あるところに影がある」で、忍者のことをそう言っているわけですが、なかなかかっこよく、記憶に残っています。
*
さて、山本さんもお書きになっているように、この場での往復書簡は10回という予定でした。したがって、この今野の回がひとまずの最終回ということになります。往復書簡は来た手紙に返事をするのですから、あらかじめ準備はできません。「おっとそう来たか」という意外性は思いのほか面白く、受け止めながらも新しい何かを出してみたい、という気持ちになります。それが山本さんいうところの「カードを出しあいながら」という感覚だと思います。山本さんと今野とは、持っているカードがかなり違いそうだということが最初からわかっているわけですが、それがまたおもしろく感じました。あっという間に最終回になったような気がしますが、貴重な時間と機会でした。ありがとうございました。そして、山本さんもお書きになっているように、こうした「対話」がこの後もどこかで続けられたらいいなと今野も希望しています。そういう気持ちをこめて、今後ともよろしくお願いします、ということばで最終回を終わりたいと思います。
2022.1.5
今野真二